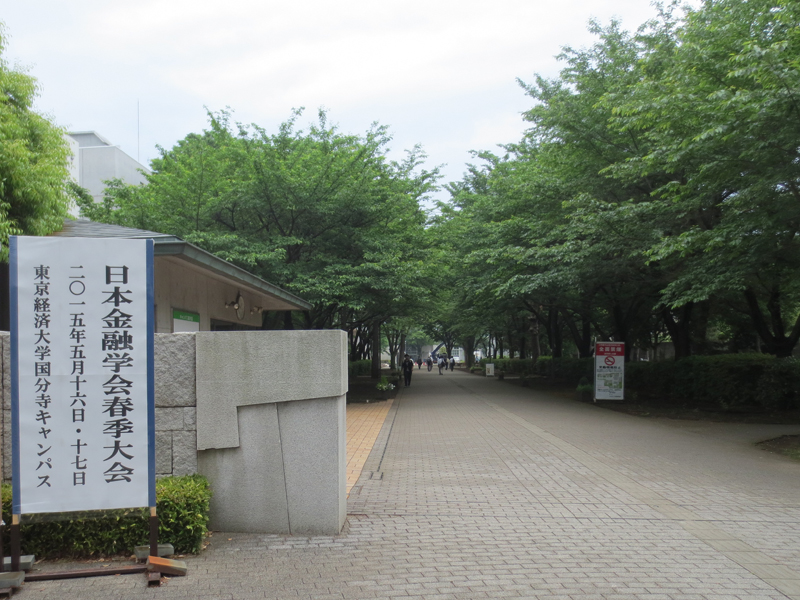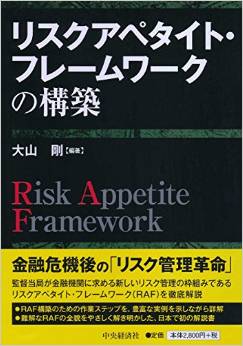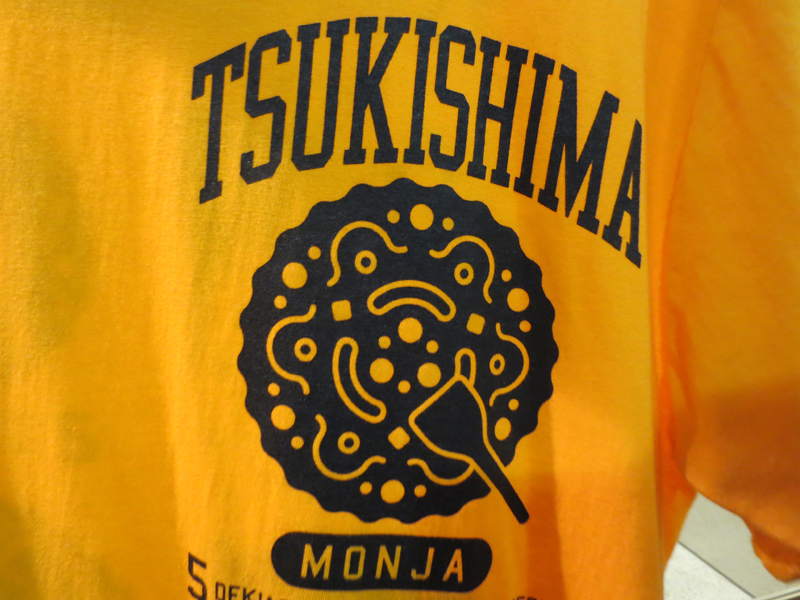保険募集規制改革の政府令・監督指針に関する
パブリックコメントの結果が公表されましたね。
「72の個人及び団体より延べ649件のコメント」だそうで、
コメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方を
取りまとめた「別紙1」はなんと245ページもあります。
担当のかたはさぞ大変だったことでしょう。
パブコメの結果は後でゆっくり読むことにして、
保険会社のガバナンスに関する資料を見つけたので
ご紹介します。日銀のサイトへ
4月に開かれた金融高度化センター主催のセミナーでは、
主に銀行のガバナンスをテーマにしたいくつかの講演や
パネルディスカッションが行われたようです。
最近になって「パネルディスカッションの模様」が公表され、
金融庁の遠藤検査局長のコメントが載っていました。
そこでは取締役会に関する分析結果が紹介されていて、
保険会社に関しては、
「1年前は、正直なところ、取締役会は『厳粛な会議の場』
ということで、あまり活発な議論が行われていない社も
ありました。フォローアップを続けてきましたが、最近では、
取締役会の運営はドラスティックに変わったという印象を
受けています」
なのだそうです。
「3メガバンク、大手生損保、そして、いくつかの地域銀行と
ガバナンス態勢に関する議論を行いました。具体的には、
取締役会、監査役会、内部監査、外部監査に関する現状と
課題について議論をさせていただき、比較分析を行いました」
とあるので、ここでの「保険会社」とは大手生損保なのでしょう。
おそらく昨年に続き6月頃に公表されるであろうレポートで、
ガバナンスに関する分析結果が示されるのではないでしょうか。
※写真は人気の武蔵小杉です。
※いつものように個人的なコメントということでお願いします。
ブログを読んで面白かった方、なるほどと思った方はクリックして下さい。