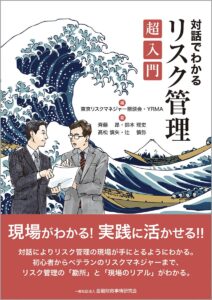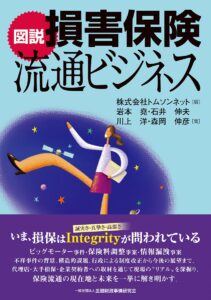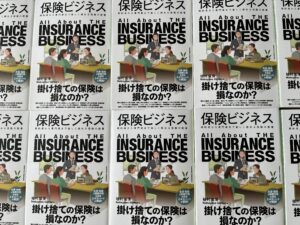日経電子版「会計士協会、生保の保有債券の会計ルール見直し案 一部減損不要に」やBloomberg「生保保有債券の会計処理を見直しへ、一部減損不要に-会計士協会」が報じたように、日本公認会計士協会は2月17日に公開草案を公表し、「満期保有目的の債券」区分に加え、「責任準備金対応債券」区分の債券についても予想信用損失モデルを適用する、すなわち、信用損失のみに焦点を当てた損失計上とする会計基準を導入する方針を打ち出しました。
2022年に入ってから長期金利の上昇基調が続き、当時は1%を下回っていた30年国債利回りが、2025年12月末には3.35%、この2月には3.58%まで上がりました。金利が上昇すれば債券価格は下落しますので、多額の超長期債を保有する生命保険会社では時価が取得原価を大幅に下回り、いわゆる含み損が拡大しています。従来の会計基準では、満期まで保有し続けるのではないのなら、責任準備金対応債券であっても減損ルールの適用となり、時価が取得原価を50%超下回った場合には損失を計上しなければなりません。新たな方針が適用となれば、信用リスクの大きい債券でなければ金利上昇に伴う減損リスクを気にしなくて済むようになります。
債券市場では生保が超長期債を買いやすくなると好感しているようですが、他方でESRの「大量解約リスク」の問題もあり、各社が金利リスクをどうコントロールしていくかは何とも言えません。
ただ、この3月末の決算から資産も負債も時価評価する新たなソルベンシー規制が入り、「実質純資産」規制もようやく廃止となり、他方で大手損保グループが相次いでIFRSを任意適用する(IFRSには責任準備金対応債券のような区分はなく、保険負債も原則として時価評価)といった状況のなかで、国内の保険会計では相変わらず資産サイドだけを見て、「時価評価する/しない」とか「減損する/しない」とかいう話に終始しているのは、なんだかなあという感じはします。
金融庁は「2025年 保険モニタリングレポート」のなかで、「経済価値ベースのリスク管理との整合性や財務会計に関する見直しの動向等も踏まえ、監督会計のあり方について、関係者を含めた検討を実施する」(37ページ)と述べています。米国とは違い、日本の保険会計(財務会計)は監督会計と同じものなので、むしろそちらの検討を加速したほうがいいのではないでしょうか。
※写真は柳川(福岡県)のさげもん(ひな祭りの飾り)です。

※いつものように個人的なコメントということでお願いします。
ブログを読んで面白かった方、なるほどと思った方はクリックして下さい。