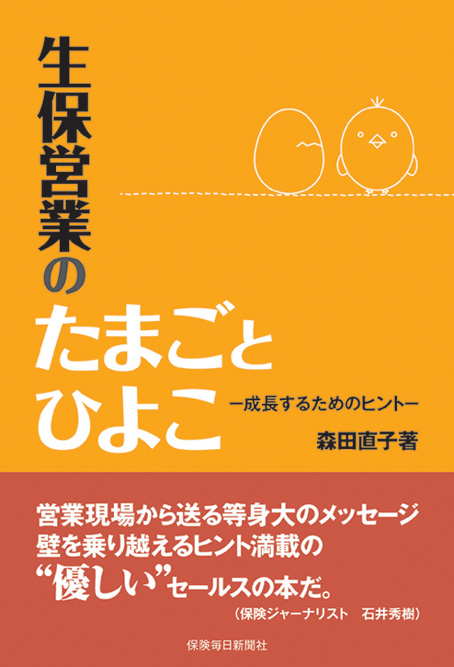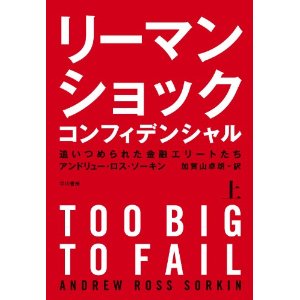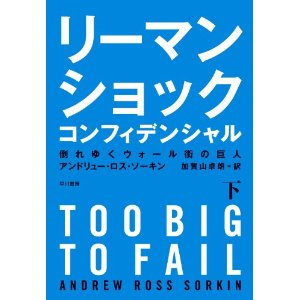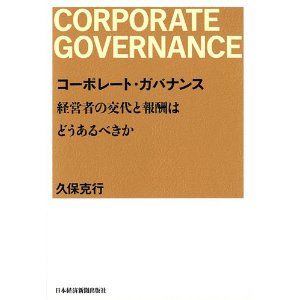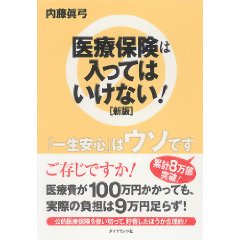慶大先導研究センター特任教授の保井俊之さんの著書
「保険金不払い問題と日本の保険行政」を読みました。
保井さんは保険金不払い問題のまさにその時期に、
金融庁監督局の保険課長として最前線にいたかたです。
本書は保険金不払い問題そのものというよりは、
問題に対して行政処分を発動した金融庁の対応をもとに、
保険行政のあり方について論じています。
私がキーワードを勝手に挙げるとすれば、
「システムズ・アプローチ」でしょうか。
不払い問題への当時の保険行政の対応について、
問題をシステムの機能不全と捉え、勘と経験ではなく、
システムズ・アプローチにより解決した先行例であると
保井さんは述べています
(意図してこの手法を用いたわけではなさそうですが)。
また、本書では金融行政を次の4つに整理しています。
①コントロール(統制)指向
②コンプライアンス(法令遵守)指向
③コンバージェンス(目標集束)指向
④コンティンジェンシー(危機管理)指向
日本の保険行政は2008年にコンプライアンス指向から
コンバージェンス指向、つまり多様なステークホルダーの
選好に応えた規制設定と執行を行うものに転換したものの、
「金融危機への対応に追われ、その転換の歩みは
遅々として進まないように見える」
「作られるルールをいたずらに厳しいものにすることは、
(中略)結果として執行のなし崩し的な取りやめで
規制の形骸化が図られ、規制の有効性そのものが
毀損される場合が多い」
といった記述もありました。
たまたま昨日(26日)金融庁が監督方針・検査基本方針を
発表しています。これらはどのような評価になるのでしょうか?
金融庁HPへ
学術書なのでスラスラ読める本ではありませんでしたが、
日本の金融・保険行政についてここまで体系的に分析し、
さらに、分析結果に基づいて政策提言を行っている本書は、
非常に貴重な存在だと思います。
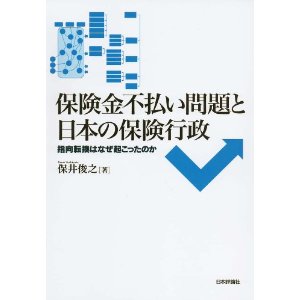
※写真は相変わらず本文とは全く関係ありません。
先日の台湾旅行の時期がちょうど中元節だったので、
町のあちこちで普通の人たちがお供えをしたり、
「お金」を燃やしたりしていました。
※いつものように個人的なコメントということでお願いします。
ブログを読んで面白かった方、なるほどと思った方はクリックして下さい。