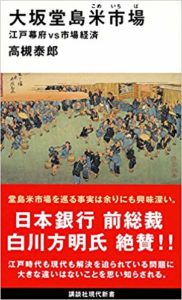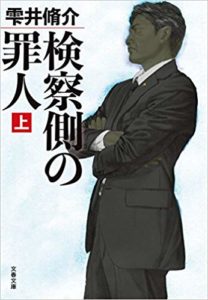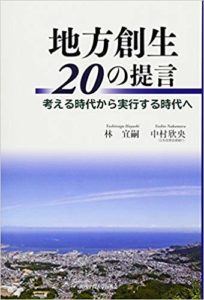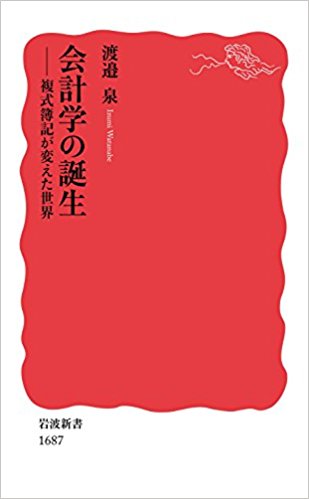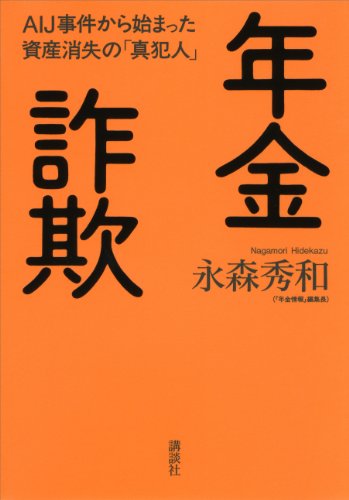損保総研・ERM経営研究会が執筆した「保険ERM経営の理論と実践」でも示されているように、3メガ損保グループは金融庁がERM(統合的リスク管理)に注目する前からERMを推進し、外部からも高い評価を得ています(格付会社S&Pの評価など)。
ERMを構築するうえで、ERMを支える企業文化、すなわち、リスクや収益の概念を軸とした議論や意思決定を行う企業文化を、経営陣だけでなく役職員全体に浸透させることは、ERMの構築を進めるうえで最も重要かつ難しい取り組みだと思います。
このERMカルチャーが組織内にどの程度浸透しているのかを知ることは、外部からはもちろん、経営陣であってもそう簡単ではなさそうですが、損保総研の機関誌「損害保険研究」第80巻第4号(2019年2月)に掲載された浅井義裕さんによる論文「ERMに関する意識調査の概要報告」では、ウェブ上で損害保険会社の社員を探し、ERMに関する意識調査を実施しています。
損保総研のサイトへ(論文の閲覧はできません)
調査では、損害保険会社に勤めていると回答した500人(うち67%が3メガ損保グループ勤務と回答)に対してERMに関する質問を行い、損保社員のERMへの意識を把握しようとしています。「概要報告」とあるので、論文にはアンケート調査のすべてが掲載されているのではなさそうですが、なかなか興味深い結果が出ています。
例えば、「ERMの考え方は、あなたの人事評価に反映されていますか?」という質問に対し、「反映されている」「ある程度反映されている」という回答は30%に達しています。また、「上司などからの指示が、『リスクを考慮しながら、リターンを追求する』を意識したものになってきていると思いますか?」に対しては、回答者の40%が「そう思う」「ややそう思う」を選んでいます。
回答者のうち、国内営業部門、営業支援部門、損害サービス部門が全体の7割を占め、保険代理店の役職員も数%含まれていることを踏まえると、これらは非常に高い数値に見えます。
他方で、「貴社におけるERMの位置付けをどのように評価されますか」という質問に対しては、クロス集計表によると、「わからない」という回答が3メガ損保の社員でも38%に上っています(全体では43%)。
同じ質問に対し、「重要である」という回答割合が3メガ損保の社員では31.5%と他の属性よりも高い(その他国内損保は18%、外資系は16%)ことから、浅井先生は論文のなかで、「ERMは3メガ損保にとって特に重要であることが確認できる」と分析していますが、私はむしろ「わからない」という回答が4割近くを占めることに興味を持ちました。
要するに、「ERMは人事評価に反映されたり、ERM的な考えが上司の指示に見えてきているけど、経営としてERMが本当に重要なのかどうかは半信半疑」と考えている3メガ損保の社員がかなり存在するいうことになりますね。
※写真は札幌市電です。環状線になって便利になりました。

※いつものように個人的なコメントということでお願いします。
ブログを読んで面白かった方、なるほどと思った方はクリックして下さい。