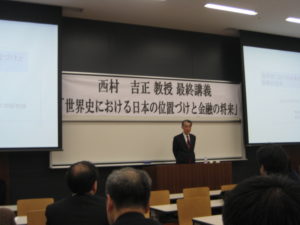2013年に政府による成長戦略の一環としてコーポレートガバナンス改革が始まってから、社外取締役を選任する上場会社が急速に増え、2名以上の独立社外取締役を選任する上場会社の比率は95%に達しています(市場第一部)。
日本証券取引所のサイトへ
この変化は率直に言ってすごいと思いつつ、当然ながら形だけ整っていても意味はないので、実質的な役割を果たせるかどうかが焦点となります。
経済産業省が7月末に「社外取締役の在り方に関する実務指針(社外取締役ガイドライン)」を公表したのも、まさにそのような問題意識からです。
ところで、第一生命ホールディングス「アニュアルレポート2020」に「社外取締役による座談会」が載っていて、読んでみると形式的なコメントばかりではなく、興味深いものでした。
例えば、次のようなコメントがありました。
「社外取締役と社内取締役の間のコミュニケーションが、質、量ともに高まっていることと、そのコミュニケーションも形式的なものではなくて、ガチンコの議論が展開できている、もしくはそうなったということが挙げられます」【朱取締役】
「社外取締役による自律的な取組みが本格的に始まり、それが定着してきたということです(中略)昨年の2月か3月頃から自発的に社外取締役全員で集まって議論するようになり、当初は食事をして懇談するところから始まったのですが、回を重ねるごとに、テーマを決めて、誰かが資料を用意しそれをもとに議論するといったことも始めました」【井上取締役】
「第一生命ホールディングスの取締役の方々は第一生命グループ全体の取締役であり、グループ全体のマネジメントに権限と責任を有しています。取締役が自己の専担範囲の業務執行はしっかりと行うが、他の取締役の担当業務にはあまり関心がない、そのような状況に将来陥っては困ります」【増田取締役】
会社からインプットをしてもらうというレベルから、社外取締役による自律的な取り組みとなってはじめて、取締役どうしのまともな議論ができるようになってきたということなのでしょう。いい流れだと思います。
※40年前に筑肥線・小笹駅があったところです。看板の前あたりだと思うのですが…
取材したところ、駅前の通りは今よりも低くて、大雨が降ると水没して大変だったそうです。

※いつものように個人的なコメントということでお願いします。
ブログを読んで面白かった方、なるほどと思った方はクリックして下さい。