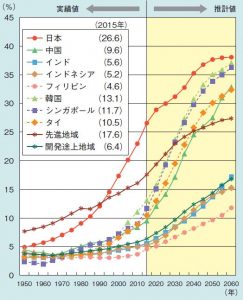前回のブログではソウルの写真だけでしたが、ソウルで開かれた韓国金融学会で、日本金融学会からの派遣者として報告をしてきました。
韓国での発表なので、世界的な超低金利のなかで、日本、台湾、ドイツ、そして韓国の大手生命保険会社の経営行動を探るというケーススタディにしました。
発表内容はどこかでお伝えする機会があると思いますが、なぜこの4か国かというと、いずれも生保市場の規模が大きいうえ、長期にわたり利率を保証する商品が生保市場の中心だったため、保険会社が資産と負債のミスマッチを抱えやすいという点で共通しているためです。
日本の大手生保が提供する主力商品は、かつてに比べると終身部分が非常に小さく、総じて期間10年程度の保障性商品の組み合わせとなっています。ただし、過去に獲得した契約による影響が依然として大きいので、金利リスクを抱えた状態が続いているのですね。
他方、今の金利上昇が長続きしないとなると、他の3か国はより深刻な状況に見えます。ドイツでは会計上も追加責任準備金の負担が年々膨らみますし、台湾では外資系生保の撤退や中小生保の経営破綻が相次いでいます。韓国は2000年代以降、利率変動型商品にシフトしてきたのですが、これらには最低保証があり、過去の高利率契約とともに生保の負担となっているようです。
こうして国際比較をしてみると、限られたディスクロージャーからでも経営行動の違いが見えてきて、興味深いです。
※写真は全州の韓屋村です。路地に入ると静かな世界が広がっていました。

※いつものように個人的なコメントということでお願いします。
ブログを読んで面白かった方、なるほどと思った方はクリックして下さい。