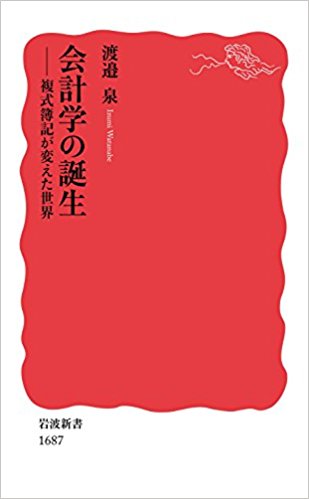岩波新書「会計学の誕生――複式簿記が変えた世界」という本が目に留まり、さっそく読んでみました(歴史学科出身ですので^^v)。著者は会計史の研究者である渡邉泉さんです。
簿記や会計の発達は、当然ながら商業の発達と密接な関係があります。
本書によると、複式簿記のルーツは中世に東方貿易や金融業などで栄えた北イタリアの諸都市(ヴェネツィア、フィレンツェなど)までさかのぼれるそうです。それ以前の「(古代)ローマ起源説」「インド起源説」もあるようですが、単なる現金の出納記録ではなく、損益計算の記録としては、13世紀初頭の北イタリアで発生したというのが著者の見解です。
当時はまだ株式会社は存在していません。しかし、血縁ではなく、他人どうしが共同で事業を行うとなると、どこかの時点で利益の分配が必要になり、損益計算が求められます。そこで、最初に実地棚卸に基づくストック計算が行われるようになり、続いて、複式簿記に基づく収益・費用といったフローの側面からの損益計算が確立していったという流れです。
19世紀初め、産業革命期のイギリスの話も興味深かったです。当時のイギリスでは、資金調達のために貸借対照表や損益計算書を作成して企業の安全性や投資の有利性を強調したり、会計上の利益と投資可能な手元現金とのギャップを埋める工夫がなされたり、新しい費用配分法として減価償却が考え出されたりと、会計進化の過程でまさに大きなエポック・メイキングとなった時代でした。優先株の発行も当時すでにあったのですね。
もっとも、僭越ながら本書を読んで違和感を感じた点もありました。
著者の渡邉さんは、次のような趣旨のことを本書で繰り返し述べています。
「ストック面からの損益計算(=資産負債アプローチ)が正しいかどうかを検証するため、フロー面からの損益計算(=収益費用アプローチ)を行うということは、フロー計算がストック計算よりも信頼に足るということを示している」
フローの損益計算がストックの損益計算の証明手段なのだから、フローの損益計算が最も信頼できる会計だという理屈が、私にはどうも理解できません。数学の世界ではこのように考えるのが一般的なのでしょうか?
「会計とは歴史的に見て、実地棚卸に基づくストック面の損益を、複式簿記に基づく収益・費用の損益計算で検証することである」と定義してしまうのであれば、(その是非はともかく)わかるのですが。
もう一つの違和感は、「近年、会計不祥事が多発しているのは、会計の役割として投資意思決定への有用性が強調され、提供する情報の信頼性が置き去りになったため」という著者の主張です。
そして本書では、有用性を重視した公正価値による資産や負債を測定する会計について、「予測による不確実な未来計算」として批判し、事実に基づく取引価格(取得原価)で客観的な情報を提供するのが会計の役割としています。
しかし、いくら取引価格が正しく記録されていても、例えば固定資産は時の経過や使用により価値が下がっていくので、そのままでは信頼性を確保できないということから、19世紀のイギリスで減価償却という手法が考え出されているわけです。
本書には、「時価評価によって一時的に資産の価値を減ずる方法とは、明確に分けて考えなければなりません」とありますが、公正価値会計も発想の根本は同じだと思うのです。何らかの人為的に決めたルールで償却を行う代わりに、決算時点ごとに正しいと見込まれる「現在価値」で評価するということなのですから。
「未来計算は不確実」として公正価値を切り捨てるのであれば、減価償却だって本当に正しい姿を表しているとは思えませんので、著者がここまで公正価値会計に否定的な理由がよくわかりませんでした。あとは、どちらが会計として企業活動の実態に迫っていると考えられるかということではないでしょうか。
とはいえ、本書を読んで、商業の中心が北イタリアからフランドル地方(ベルギー)、オランダ、イギリスへと変わるとともに、簿記や会計も進化してきたことなどを知り、簿記や会計の歴史をたどることは、すなわち、商業都市の盛衰をたどることだと気づかせてくれる、興味深い本でした。
※前回に続き、地元の写真です(大倉山公園)。