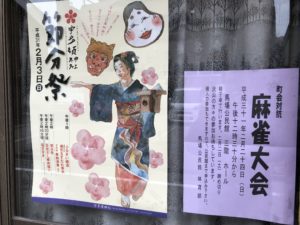少し前に、2018年に日本を訪れた外国人が3119万人に達したというニュース(16日に日本政府観光局が発表)がありました。短期間でここまで増えるとはすごいですね。
出国者も過去最高を更新
ところで、この日本政府観光局の資料をよく見ると、日本から海外に出かけた人数も1895万人と、2012年の1849万人を超え、過去最高を更新しています。
過去の推移を確認したところ、2000年の1781万人までは概ね右肩上がりで増えていましたが、その後は増えたり減ったりという感じです。2012年は円高が後押しとなり、2013年からは反対に円安が足を引っ張ったようです。ここ数年の増加は為替要因ではなく、後述する世代要因が大きいのかもしれません。
訪問先は大きく変化
興味深いことに、海外旅行の訪問先は2000年頃とはかなり異なっていることがわかりました。出国者数に占める主な訪問先の割合を2000年と2016年で比べると、次のとおりです
(各国統計の寄せ集めなので、あくまで参考としてご覧ください)。
中・韓・台・香港
37% ⇒ 44%
米国(ハワイを含む)
28% ⇒ 21%
欧州(7か国)
25% ⇒ 15%
東南アジア(8か国)
21% ⇒ 28%
要するに欧米が減って、アジアが増えたということですね。
ドイツは当時の6割、フランス、イタリア、イギリスは当時の5割まで減っています(スペインは増加)。昨年私たちが訪れたスイスは、かつては100万人近い日本人が旅行していたそうですが、近年は20万人前後です。
リゾート地として落ち込みが激しいのが北マリアナ諸島(サイパンなど)で、当時の2割弱の水準です。グアムも当時の約7割。ハワイは当時の8割強で、近年は回復基調です。
他方で2000年に比べて増加が目立つのは、何といっても台湾です。いまや200万人近い人が訪れています(当時は90万人程度)。中国と韓国はいったん増えて、その後もとの水準に戻っています。
東南アジアではベトナムの増加が目立ちます。当時の15万人から最近は80万人にまで急成長しました。書店に行くとベトナムのガイドブックをよく見かけるようになったので、ビジネスだけでなく、観光客が増えているのでしょう。

若者は海外に行かなくなったのか
ところで、ひところ「若者が海外に行かなくなった」という話をよく耳にしました。20代の出国率をみると、確かに1990年代後半から2000年代にかけて低迷が目立ちました。
ところが、2010年代はむしろ回復傾向で、2017年は過去最高を更新しています。
1990年代後半から2000年代前半はちょうど就職氷河期にあたり、非正規雇用も増え、海外に行きたくても行けなかった20代が多かったのではないでしょうか。企業が出張費を抑えたということもあるでしょう。これに対し、2010年代は就職面では売り手市場が続いていますし、企業の海外進出(特にアジア)も拡大しています。LCCの相次ぐ就航も出国を後押ししているかもしれません。
さらに、親子の年齢差を30歳くらいとすると、今の20代の子どもを持つ親は50代ということで、自分たちが20代のときに海外に出かけたり、子どもと一緒に海外へ行ったりした経験が、それ以前の世代よりも多いと考えられます。
いずれにしても、20代人口の絶対数が減っているので目立ちませんが、総論としての「若者が海外に行かなくなった」という認識は改めたほうがよさそうです。
※ミャンマーへの日本人旅行者も急増しています

※いつものように個人的なコメントということでお願いします。
ブログを読んで面白かった方、なるほどと思った方はクリックして下さい。