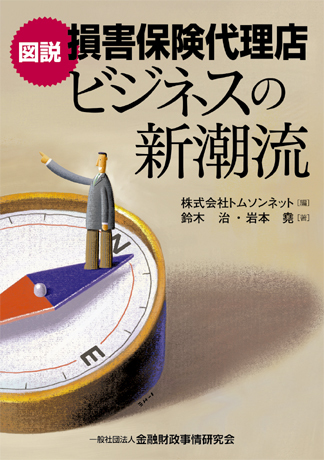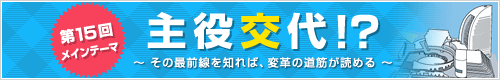「日本型リーダーはなぜ失敗するのか」を読みました。
著者は半藤一利さん。文春新書です。
昭和史と太平洋戦争の「歴史探偵」である著者が、
太平洋戦争の教訓からリーダーの条件を考えたものです。
資料調査と当事者への取材に基づいた記述が多く、
読みやすい本でした。
日本型リーダーシップとは、「参謀が大事」という考えです。
その起源は戊辰戦争と西南戦争にあります。
「総大将は戦いに疎くても参謀さえしっかりしていれば勝てる」
二つの成功体験がこの考え方を決定づけました。
さらに日露戦争の勝利です。
後にリーダーの理想像とされた「海の東郷」「陸の大山」は、
実際には参謀の上にただ乗っかっていたわけではなく、
戦場では指示を出し作戦を指揮していたようです。
それにもかかわらず、「威厳と人徳」のリーダー像が
作られていきます。
日露戦争の大勝利の栄光を汚さないため、
だまって部下の作戦・行動を見守る静かにして重々しく
堂々たる総大将が日本型リーダーの理想像とされていきます。
参謀任せの「太っ腹リーダー像」が生み出され、
「威厳と仁徳」の将を支えるために参謀重視となり、
上が下に依存する習慣が通例となりました。
その結果、本当の意思決定者がわからなくなり、
権威を笠にきて権限を振り回す参謀が輩出され、
根拠なき自己過信や傲慢な無知、底知れぬ無責任が
戦場でまかり通ったとか。
著者は、エリート集団による「独善性」「硬直性」「不勉強」
「情報無視」は現在に通じていると述べていますが、
残念ながら同感です。
※写真は伊豆の代官・江川家です。
NHK大河ドラマ「篤姫」で篤姫の実家として使われたとか。
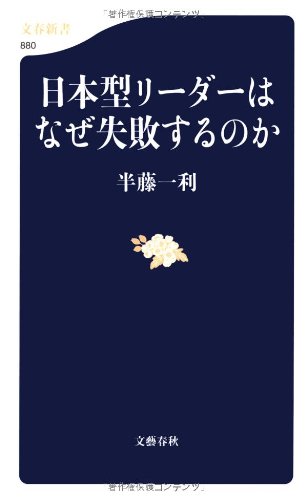
※いつものように個人的なコメントということでお願いします。
ブログを読んで面白かった方、なるほどと思った方はクリックして下さい。