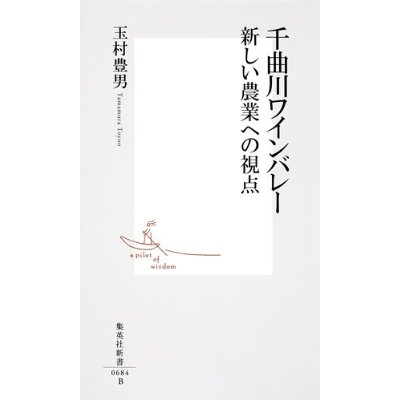「ビジネスマンのための『行動観察』入門」を読みました
(著者は松波晴人さん。講談社現代新書です)。
「行動観察」とは、観察者が様々なフィールドに入って
対象となる人間の行動をつぶさに観察したうえで分析し、
問題解決法を提案する手法のことです。
アンケートやグループインタビューでは、主として
顕在化しているニーズやリスクを収集することになります。
これに対し、行動観察では本人がそうと認識していない
課題やニーズを知ることができます。
「今どんなリスクに直面していますか」と聞かれても、
それがリスクだと気が付いていなければ、回答しませんよね。
さらに、行動観察では、アンケートやインタビューで生じがちな
バイアスを排除することもできます。
本書では「アンケートでは社会通念に反する回答は出てきにくい」
とありました。確かにそうかもしれません。
ただ、行動観察が十分な効果を上げるかどうかは、
どうも観察者の力量によるところが大きいように感じました。
本書で観察の対象となった現場は、「販売イベント会場」
「営業マンの行動」「残業だらけのオフィス」「飲食業」「書店」などで、
筆者のチームはそれぞれでかなりの成果を上げているのですが、
やはり観察経験を踏むほど、成果が上がっているようです。
著者も、観察者が学ぶべき二つのポイントとして、
・自分の価値観から自由になる
・人間についての知見を持つ
を挙げ、どちらも大変な労力と時間がかかると述べています。
とはいえ、「フィールドを観察し、よい仮説を立て、それを検証する」
という自然科学の流れをビジネスで応用するという「行動観察」は、
ERMの構築サポートでも応用できそうです。
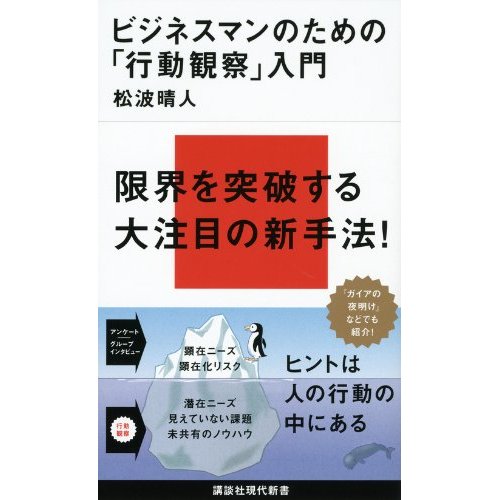
※連日天気が悪いので、このような月がなかなか見られませんね。
※いつものように個人的なコメントということでお願いします。
ブログを読んで面白かった方、なるほどと思った方はクリックして下さい。