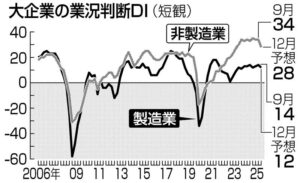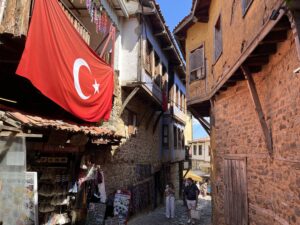バタバタしていて1週間あいてしまいました。今週から来週にかけては東京・横浜で過ごしています。
さて、8月6日に金融庁(東海財務局・関東財務局)が、中古車販売大手の大型兼業代理店であるネクステージと、「マネードクター」を展開する保険専業代理店であるFPパートナーにそれぞれ行政処分を行いました(いずれも業務改善命令)。
ネクステージへの行政処分
FPパートナーへの行政処分
ネクステージへの行政処分
同社は2023年に旧ビッグモーター事件を受けて自主調査を行い、不正請求事案は確認されなかったと公表しています。その後、主要取引銀行の要請で外部弁護士による調査を行い、やはり不正請求事案は確認されなかったと報告しています。
しかし、今回の立入検査で、「調査担当の従業員は各々の主観に基づいて関係資料を確認し、問題がないとの判断を裏づける証拠も残していない」「関係資料が揃っていないなど不正請求の蓋然性がより高いと考えられる案件を調査対象外にしている」「調査対象期間外に発生した不正請求事案を把握していても、全容解明に向けた伏在調査を行っていない」「損害保険会社の調査で不正請求疑義事案を把握していても、事実確認のための調査の指示を行っていない」などが明らかになり、東海財務局は「現在でも不正請求事案が多数内在している蓋然性が高い」と判断しました。
問題の根底には、同社の経営陣が保険事業の重要性を認識しておらず、保険業法等の知見も欠如しているため、保険事業に関するガバナンスが機能不全となっていることがあると指摘しています。
1月に行政処分を受けたトヨタモビリティ、グッドスピードと同様に、この会社(あるいはこの業界)がこのまま保険代理店を続けていいのか疑問に感じる内容です。
日本損害保険業界は代理店業務品質評価制度を導入し、全ての代理店が自己点検チェックを行ったうえで、第三者機関が必要と判断した代理店を対象に第三者評価を行う方針です。しかし、問題が発生していてもまともな調査をしない(あるいはできない)ような会社に対し、関係者には申しわけありませんが、ある意味で性善説に基づいたこの評価制度の枠組みが果たして機能するのでしょうか。
FPパートナーへの行政処分
リリースによると、同社は訪問型の保険代理店としては業界最大手で、複数の保険会社の商品を比較推奨するビジネスモデルをとっています。同社は2024年6月に関連する開示を行い、①商品の優位性 ②商品提案の難度 ③保険会社の顧客サポート体制を総合的に判断し、各商品への社内評価を設定しているとしています。
しかし、実際には「保険会社からの便宜供与の実績に重点を置いて推奨商品の選定を行っている」「(医療保障を希望している顧客に対し)合理的な理由なく特定の保険会社を偏重して推奨していることが強く疑われる」など、保険会社からの便宜供与の実績を重視した保険募集管理態勢を構築していると関東財務局は判断しました。
ちなみにFPパートナーは、生命保険協会が2022年に導入した代理店業務品質評価において、2024年に評価基準の基本項目を全て達成した代理店として認定されています(2025年2月に評価結果を停止)。
業界団体による評価がダメで、当局の検査が絶対正しいと言うつもりはありませんが、書類審査とヒアリングを中心とした評価では、評価を受ける側は当然ながら自分に都合の悪いことは言わないので、なかなか難しいものがあるのでしょう。
※写真は福井です。

※いつものように個人的なコメントということでお願いします。
ブログを読んで面白かった方、なるほどと思った方はクリックして下さい。