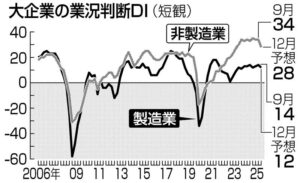このところ大手損害保険会社の決算は政策保有株式の売却益計上で(少なくとも表面的には)好調が続いています。これを見た保険流通に関わるかたから、「株式購入の原資は契約者の保険料なのだから、保険会社は政策保有株式の売却によって得られた利益を保険料の引き下げという形で契約者に還元すべきではないか」という質問(意見?)をいただきました。
最初に結論を述べれば、株式会社形態の保険会社であれば、株式投資によるリターンは原則として株主のものと考えるべきで、これを契約者に還元しなければならない理由はありません。
株式会社形態の保険会社では、株主は保険引受のリスクやそれに伴う資産運用のリスクなど、経営全てのリスクを負っています。株主が政策保有株式のリスクを経営にとってほしかったかどうかは別にして、リスクをとった結果として得られたリターン(より正確には、時価ベースの純資産)は、まずは株主のものです。
これに対し、契約者は保険会社の破綻リスクのみを負う「債権者」という位置付けです。保険債務の責任を果たせば、経営にはそれ以上の責任はありません。
もし、保険料を下げることで、中長期的にはより多くのリターンが得られるという考えに株主が納得すれば、料率引き下げという経営判断もあり得ます。しかし、それはあくまでも、さらなるリターンを目指すための料率引き下げであって、契約者への還元ではありません。
他方、保険料率の計算にあらかじめ資産運用収益を含めておくというのは、保険ビジネスとして健全な経営ではありません。保険会社の資産運用がうまくいかなかった場合に、保険会社は保険金額を減らしたり、契約者から追加で保険料を集めることができないからです。
長期の保険では一定の利率(予定利率)で増えていくことを前提にしたものが一般的ですが、これは資産運用収益を当てにしているというよりは、貨幣の時間価値を考慮している、つまり、将来のお金を現在価値に換算しているものです。
株主はそもそも資産運用で収益を上げるのを生業としています。ですから、バフェット氏のような資産運用に強みを持つ保険会社でもないかぎり、「資産運用に頼るのではなく、得意分野である保険ビジネスでリターンをあげてほしい」と考え、保険でリターンを上げられないのなら、そのビジネスをやめてほしいと考えるはず。
株式会社の保険経営者は、もちろん契約者をはじめとした利害関係者にも目配りする必要がある(法令等の遵守を含む)とはいえ、株主の期待に応えるために存在しています。
ちなみに、相互会社形態や協働組織であれば契約者への還元は重要な選択肢の1つです。なぜなら、これらの組織では、契約者は債権者であるとともに、組織のオーナーでもあるからです。
※週末の嵐山はすごい混雑でした!

※いつものように個人的なコメントということでお願いします。
ブログを読んで面白かった方、なるほどと思った方はクリックして下さい。