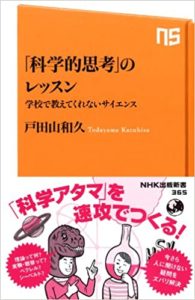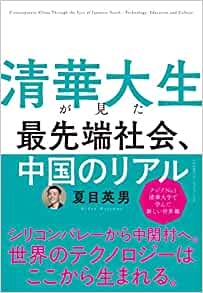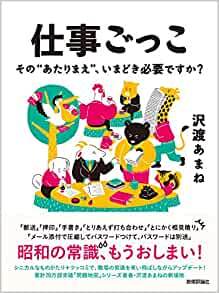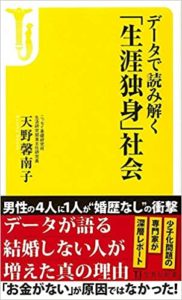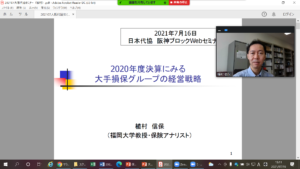今週のInswatch Vol.1115(2021.12.13)に生保決算に関する記事が載りましたので、ご紹介いたします。
——————————
11月に各社の決算発表がありましたので、今回は主に新契約年換算保険料(新契約ANP)のデータから、長引くコロナ禍における各社の業績がどうだったのかを探ってみました。
大手生保:営業職員チャネルはコロナ前の8割程度か
昨年度のこの時期(2020年4-9月期)は営業活動の自粛により業績が大きく落ち込んだため、今回のデータを前年と比べてもあまり意味はありません。では、コロナ前の一昨年度(19年4-9月期)と比べればいいかといえば、ご存じのとおり、19年2月の「バレンタイン・ショック」で法人向け保険の販売が大打撃を受けた時期にあたります。足元の回復状況をつかむには、もう少し長い期間を見て判断する必要がありそうです。
そこで、まずは営業職員チャネルを主力とする大手生保(日本、第一、住友、明治安田)について、個人保険の新契約ANPを20年度、19年度、18年度、17年度と比べてみました。
【日本】 159 111 88 65%
【第一】 230 96 88 71%
【住友】 136 84 70 66%
【MY】 126 103 72 89%
日本生命の場合、新契約ANPが昨年度よりも59%増え、19年度と比べても11%増えています。しかし、18年度対比では12%少なく、17年度対比では35%も少ない状況です。19年度に比べるとコロナ前まで回復したように見えますが、日本生命は法人向け保険の販売に積極的だったので、それが落ち込んだ19年度対比でプラスになったと考えられます。
第一生命は昨年度の営業自粛期間が長かった影響が20年度対比の数値に表れていて、18年度対比では12%減、17年度対比では29%減でした。住友生命や明治安田生命は本体で銀行窓販に力を入れているため、その影響も考慮する必要があります(明治安田生命はチャネル別の数値を公表)。
いずれにしても、営業職員チャネルによる個人向け販売はまだコロナ前には戻っておらず、ざっくり言って8割程度と見るのが妥当かと思います。
損保系生保:回復は遅い
【あんしん】 132 132 61 51%
【MSA 】 111 94 53 69%
【ひまわり】 116 109 73 72%
同じように損保系生保3社のデータを見ると、18年度や17年度対比では、先ほどの大手生保よりも低い水準です。
損保系生保の主力チャネルは損保代理店のクロスセルに加え、生保プロ、保険ショップです。生保プロを中心にバレンタイン・ショックの影響を強く受けて以降、それを補うほどの業績を挙げられていないとうかがえます。
ただし、第三分野の新契約ANPは18年度や17年度対比で伸びている(MSA生命は17年度対比のみプラス)ので、収益性はむしろ高まっているものと考えられます。
非対面販売へのシフトは進んでいない?
昨年の4-9月期は自宅にいる消費者が多かったためか、いわゆるネット生保が業績を伸ばしました。この4-9月期を見ると、アクサダイレクト生命の新契約ANPは前年対比で17%増と2ケタ成長を続けたものの、ライフネット生命はほぼ横ばい、SBI生命は7%減でした。他にもネット販売に注力しているとみられる会社の業績は軒並み低調でした(ネット販売が低調だったかどうかは不明です)。
当時の「第1波」に比べると、21年4、5月の「第4波」や7-9月の「第5波」のほうが、感染者数がはるかに多かったのですが、生命保険の巣ごもり需要は高まらなかったようです。日本では幸いコロナによる死者数が国際的にみて少ないがゆえに、コロナで生命保険のニーズが高まるようなこともなく、ネットで保険加入という流れが続かなかったと考えられます。
9月に公表された直近の「生命保険に関する全国実態調査」(21年4~5月調査)によると、今後加入するなら「インターネットを通じて」という回答が17%と過去最高となり(18年調査では12%)、「保険代理店の窓口や営業職員」という回答(12%)を上回っています。
チャネル別の業績データがないので、ネット販売に注力する会社の決算数値などからの推測ですが、潜在的にはネット加入のニーズがあるとはいえ、コロナを契機に非対面チャネルへのシフトが急速に進んでいるという状況ではなさそうです。
——————————
※写真は博多駅です。
※いつものように個人的なコメントということでお願いします。
ブログを読んで面白かった方、なるほどと思った方はクリックして下さい。