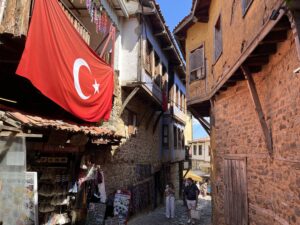保険代理店向けメールマガジンInswatch Vol.1312(2026.1.12)に寄稿した記事を当ブログでもご紹介いたします。
大学の冬休みは短く、年末はクリスマスの12月25日まで授業があり、新年は1月5日から授業を再開しています。
————————————
保険・年金サービス収支の赤字拡大
皆さま、本年もよろしくお願いいたします。
ところで、1月7日付け日本経済新聞「保険収支の赤字 年3兆円 海外企業への手数料急増(有料会員限定)」(あるいは電子版の「海外再保険料、支払い10年で9倍 収支赤字は年3兆円超」(同))という記事をご覧になったでしょうか。国際収支統計の経常収支の1項目であるサービス収支において、保険・年金サービス収支の赤字が年々拡大しているというものです。
損害保険分野での再保険手数料というと、出再会社が支払うのではなく、契約獲得費用の補填として受再会社から受け取る手数料のことを指します。トーア再保険の用語集によると、生命再保険には出再会社が受再会社に支払う「再保険者事務手数料」もあるようですが、それにしても年間3兆円もの赤字というのは大きい数字です。
計上方法に疑問あり
そこで、日本銀行国際局が2022年3月に作成した「国際収支関連統計:項目別の計上方法」で「保険・年金サービス」の計上方法を確認したところ、次のとおりでした。
・発生主義で認識した保険料に保険サービス比率を乗じて推計
(保険サービス比率は、事業費の保険料収入に対する比率)
・ただし、生命保険や年金についてはサービス部分の推計を行っていない
・生命保険や年金の保険料および保険金は、契約者の金融資産として「金融収支」のなかの「その他投資」の「保険・年金準備金」に計上
損害保険の場合には、出再会社が支払う再保険料のうち、付加保険料に相当する部分をサービス収支の保険・年金サービスに計上しているとのことです。もっとも、海外再保険のデータを確認すると、出再保険料が10年前に比べてかなり増えているとはいえ、受再保険料もありますし、収支への影響はおそらく0.2兆円程度のマイナスとみられます。
他方で生命保険については、海外出再分の再保険料をそのまま計上しているのではないかと想像していたところ、日銀の説明には「サービス部分の推計を行っていない」「保険料は金融収支に計上」とあるので、文字通り解釈すると再保険料ではないと読めます。とはいえ、出再を実施した会社の公表資料には再保険料としか記載がなく、損益計算書のどこか別のところに「支払再保険手数料」といった大きな項目があるようにも見えません。もしかしたら、既契約ブロックの出再に関する再保険料は保険料ではなく、手数料とみなしているのでしょうか。そうだとしたら、これを主因として「保険収支の赤字」となってしまうのは妙な話ですね。
再保険を使った資産運用
生命保険会社の再保険料は、10年前には年間2兆円程度だったものが、この5年間で急速に増加し、23年度からは10兆円規模に達しています。再保険料には国内会社どうしの取引も含まれるものの、増加の大半は海外への出再です。
昨年11月の投稿記事でご紹介したように、近年、生命保険会社による資産集約型再保険という取引が増えています。11月の記事で筆者は、「この取引の本質は、規制が求めるソルベンシー比率の改善という『おまけ』のついたファンド投資であって、投資先の不透明さや流動性の低さ、リスク対応の難しさなど、かつてのサブプライム問題を彷彿させるものがあります」と述べています。ファンド投資の1形態とみればいいのかもしれませんが、引き続き注目していくつもりです。
————————————
※写真は鎌倉の瑞泉寺です。

※いつものように個人的なコメントということでお願いします。
ブログを読んで面白かった方、なるほどと思った方はクリックして下さい。