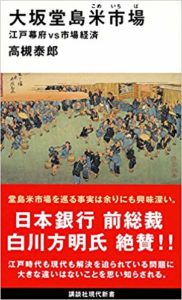直近のinswatch Vol.958(2018.12.10)に執筆した記事「『業績の安定』とは何を意味するのか」のご紹介です。損害保険会社の経営について書いています。
---------------
支払い額は過去最大に
自然災害に伴う損保業界の保険金支払いが、前回(10月8日)の本誌で、「場合によっては、年度別の支払い額が過去最高となった2004年(7449億円)に匹敵することもあるのかもしれません」と書いたところ、ご承知のとおり、これを大きく上回る1兆円規模の保険金支払いとなることが判明しました。
ただし、自然災害の発生トレンドをどう見るか、つまり、まだ過去のトレンドの延長線上と言えるのか、あるいは、地球温暖化などの影響でトレンドが変わってしまったと見るべきなのかは、見解が分かれている模様です。
日経新聞の社説
ところで、11月24日の日本経済新聞に「損保は異常気象対策を万全に」という社説が載ったのをご存じでしょうか。
「災害が相次ぐ日本を地盤とする日本の損保は、保険金支払い能力を盤石にするのはもちろん、業績を安定させるあらゆる努力が欠かせない」としたうえで、業績安定のため、損保業界が異常危険準備金の税制優遇拡大を求めていることと、火災保険の料率引き上げを目指していることを紹介しています(後者については「コスト削減の徹底が前提」だそうです)。
ここで言う「業績」とは、決算における純利益のことです。事業として自然災害リスクを積極的に引き受けている保険会社にとって、本当に「業績の安定」が欠かせないのでしょうか。
「業績」は会計ルールに左右される
自然災害に伴う多額の支払いが見込まれる状態で決算を迎えた9月期決算では、3メガ損保の国内損保事業が赤字または大幅減益となりました。前回書いたように、9月に発生した自然災害は支払いに至っていないケースが多いため、異常危険準備金の取り崩しがほとんどなかったためです。
他方で通期の決算では、支払いが進み、異常危険準備金を取り崩すため、「業績」予想は総じてそれほど悪くありません。
損保の経営にとっては(税制優遇の話を除けば)同じ自然災害により発生した支払い義務なのに、会計ルールがそうなっているというだけで、「9月期の業績は悪化」「通期では安定」というのはおかしな話ですが、社説をはじめ、メディアの多くは(結果として)こうとらえているようです。
似たような話は保有する国内株式についても生じます。
有価証券の減損を、3メガ損保のように30%ルール(期末日の時価が取得原価に比べて30%以上下落したものを対象)の会社と、原則通り50%ルールを適用している会社では、同じ銘柄の株価が下落しても、「業績」に与える影響が大きく異なることがあります。
「業績の安定」という見方をやめるべき
もし本当の意味で業績を安定させるのであれば、異常危険準備金を追加的に積んだり、保険料の値上げを理解してもらうべく踏み込んだコスト削減を行ったりしても大きな効果はありません。むしろ、日本の自然災害のようなリスクの大きい引き受けをしなければいいという結論になります。
モノラインであれば別ですが、総合的な保険会社であれば、自らの存在意義を考えた際、自然災害リスクを引き受けないという選択は考えにくいでしょう。少なくとも現時点では事業として成り立つと考えているからこそ、各社は風水災害のリスクの引き受けを続けているのだと思います。
そうだとすると、日本の損保は何年かに1回は多額の支払いが発生するのが普通の状態ということになります。もちろん、会社としてリスク分散やリスクヘッジを進め、経営を安定させる(すなわち、経済価値で見た損益の振れを経営陣が想定したレベルに抑え、資本コストを小さくする)という戦略はあります。しかし、メディアが「業績を安定させるあらゆる努力が欠かせない」などと無理に毎期の決算の安定を求め、それに応じたりすると、かえって経営を歪めることになりかねません。
※丸の内で見かけたクリスマスツリーです。

※いつものように個人的なコメントということでお願いします。
ブログを読んで面白かった方、なるほどと思った方はクリックして下さい。