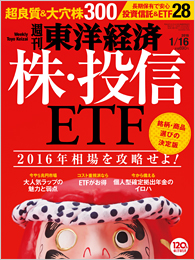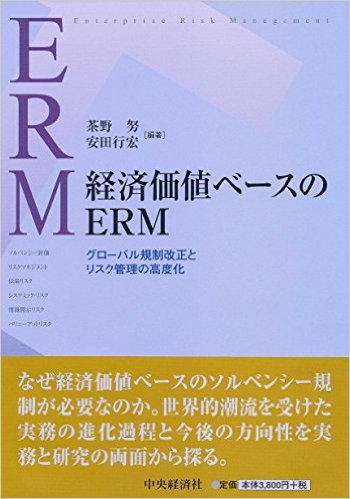数年前からアドバイザーを務めているRINGの会が
今年も横浜でオープンセミナーを開催します。

最近、「撤退戦の研究」(半藤一利さんと江坂彰さんの対談)
という本を読んだのですが、そのなかで、
「日本軍は情報に対する重要性を認めていなかった」
というくだりがあります
(第2章 なぜ情報が軽視されるのか)。
例えば、太平洋戦争の開戦2年前のノモンハン事件で
日本軍(陸軍)はソ連軍と戦って大敗しました。
しかし、昭和史に詳しい半藤さんによると、当時の陸軍は、
「日本軍は日露戦争時代の旧式の銃を使っていた」
「ソ連軍は戦場に戦車や大砲を大量に持ち込んでいた」
などの敗因から学ぶべきことがあったにもかかわらず、
戦訓は「必勝の信念をますます強くせよ」という精神論に
なってしまったそうです。
江坂さんも、
「当時の陸軍の情報不足と情報収集の怠慢ははっきり
している。そのことが装備のイノベーションを遅らせ、
昭和16年の開戦に2年先立つノモンハンの戦いを
残酷無残なものにした」
「ノモンハンとは近代戦を知るチャンスだった。しかし、
近代戦を学ばず、”国軍伝統の精神主義”を再確認
するだけに終わってしまった」
と応じています。
日本は昭和8年に国際連盟を脱退し、一種の鎖国状態と
なりました。そのなかで情報を自ら得ようともせず、
せっかくのチャンス(ノモンハンの大敗)からも学ぼうと
しないのであれば、結果は見えています。
ビジネスの世界も同じではないでしょうか。
保険流通が激しい変化に見舞われているなかで
情報収集を怠れば、たちまち当時の日本陸軍と
同じ状況に陥ってしまいます。
自分たちの明日を考えるための情報は、
誰かが与えてくれるものではありません。
さらに言えば、せっかく情報を集めても、
分析しなければ役に立ちません。
オープンセミナーに参加すれば、通常の業務では
得られない情報に接することができるでしょう。
ただし、情報に接して、それをどう活用するか。
当時の日本軍はこの点でも相当問題があったようです。
RINGの会は保険流通に関わる有志の皆さんによる
自主的な情報交流の場です。RINGの会のサイトへ
この会に参加すれば、通常ではつながらないメンバーと
横のつながりを作ることができます。
メンバーとの交流を通じて得られるものもあるでしょう。
ということで、今回は、セミナー参加だけではなく、
RINGの会にも入ってみたらいかが、というお誘いでした
(セミナー会場にRINGの会のブースがあると思います)。
※写真は中目黒駅から見た桜です(4/6撮影)
※いつものように個人的なコメントということでお願いします。
ブログを読んで面白かった方、なるほどと思った方はクリックして下さい。