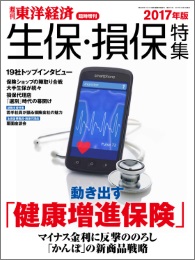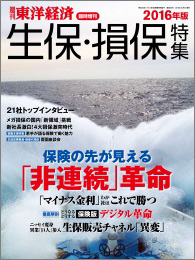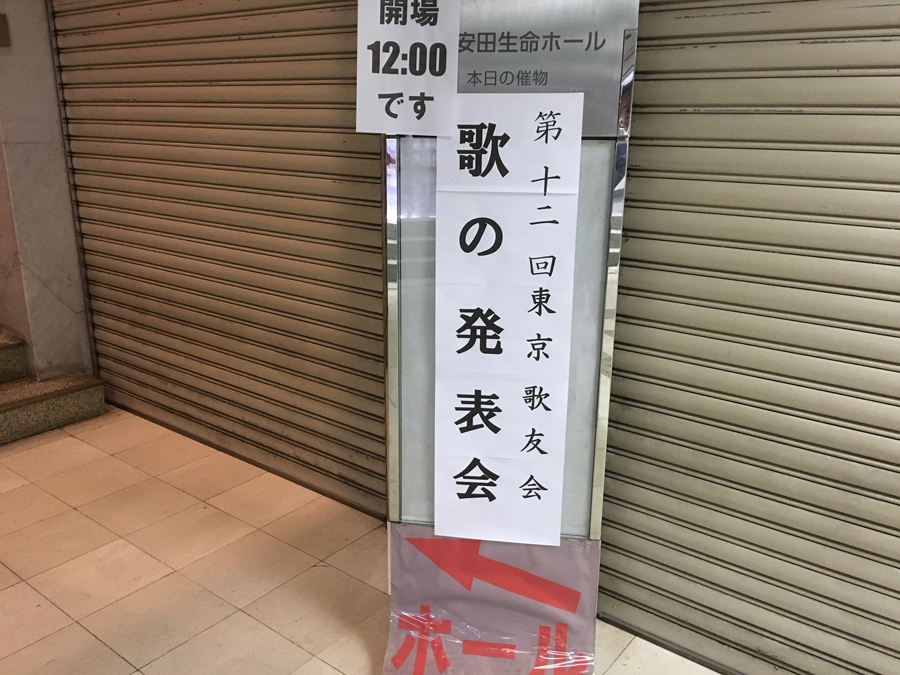うっかりしていて、8月のインシュアランス生保版に書いたコラムのご紹介を忘れていました。遅まきながらご覧ください。
————————————–
「顧客本位の業務運営」を生かす
NHK総合テレビ・クローズアップ現代+の保険特集「保険値上げで家計直撃!賢い見直し術とは」(6月28日)にゲスト出演した時のこと。
番組前の打合せで、「(保険ショップなどに対する)規制が入ったとはいえ、代理店はあくまで保険会社を代理する存在であることは押さえておきたい」というコメントをしたところ、キャスターから「それでは消費者はどこで保険の相談をしたらいいのでしょうか」と聞かれ、答えに窮した。
保険ショップをはじめ、保険会社の営業職員や代理店、銀行や郵便局の窓口など、保険について無料で相談できるところは多い。言うまでもないが、相談が無料なのは保険販売による手数料や報酬で事業が成り立っているからである。
番組のVTRでは消費者が独立系ファイナンシャルプランナー(FP)に保険の見直しを相談していた。しかし、現状は相談業務だけでFPが成り立つ環境とは言い難く、保険販売などの手数料ビジネスに依存していないFPは極めて少ないと聞く。
長い目で見れば、「適切なアドバイスをするにはコストがかかる」「情報はタダではない」という常識を消費者に浸透させる必要があるとはいえ、今の状況がすぐに変わるとは思えない。
そこで次善の策として浮上するのは、顧客本位の業務運営を掲げ、「専属」「乗合」などの自らの立ち位置や、「どのような考えのもとで保険を勧めるか」といった方針を明らかに示した販売会社への相談である。消費者の信頼を得るには、可能なかぎり具体的で納得感のある運営方針が求められる。
販売会社からすると、昨年の改正保険業法施行に続き、金融庁が打ち出した「顧客本位の業務運営に関する原則」への対応も求められ、ウンザリしているところかもしれない。
しかし、保険の相談をしたいという消費者のニーズがあり、かつ、(保険会社からの手数料に依存していないという意味で)中立的な相談窓口が少ないのであれば、消費者に顧客本位の業務運営を訴えることができる販売会社には、むしろ顧客の信頼を勝ち得るチャンスと捉えることができよう。専属チャネルでも、相談の過程で消費者にネット等を通じて他社と比べてもらえばいい。
もちろん、金融事業者等に顧客本位の業務運営を求めることで消費者利益を高めるには、販売会社をはじめとする金融事業者等の努力だけでは不十分であり、同時に消費者の金融・保険へのリテラシー向上が前提となる。行政はそのことを十分理解してほしい。
私は番組で、消費者は「自分を知ること」「社会保障を知ること」「保険の得意分野を知ること」が重要という趣旨のことを述べた。
自分を知るとは、保険であれば、自分がどのようなリスクに備えたいと考えているかを把握することであり、これは販売会社がサポートできる内容でもある。
「顧客本位の業務運営」を規制対応ではなく、ビジネスチャンスとして取り組んでみてはいかがだろうか。
※都心でもだいぶ木々が色づいてきました。
※いつものように個人的なコメントということでお願いします。
ブログを読んで面白かった方、なるほどと思った方はクリックして下さい。