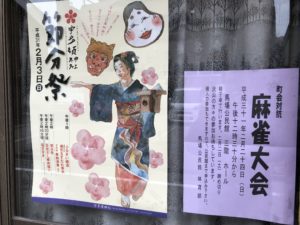昨年11月の日本アクチュアリー会・年次大会の報告集が公表されました。
すでに昨年11月11日のブログでも簡単にご紹介していますが、登壇したパネルディスカッションの内容が公表されていますので、改めて取り上げてみましょう。
金融危機を知らない世代が増加
パネリストとして登壇したのは11番のERM委員会「経済危機とリスク管理~これからのリスク管理を担う若手のために~」です。
PGF生命の鈴木理史さんが若手の実務担当者の代表として、今のリスク管理の実務に関する疑問をベテラン2人(みずほ証券の藤井健司さんと私)にぶつけるという企画でした。
この企画の背景には、若手の実務家にはバブル経済どころかグローバル金融危機も日本の保険危機もピンとこないという現実があります。中堅生保が相次いで破綻したのは20年前ですし、リーマンショックからも10年たちました。
しかも、こうした危機をも踏まえつつ築かれていった各社のリスク管理の枠組みや当局による健全性規制は、彼らにとっては初めから存在するものなのですね。
若手担当者からの悲鳴と警鐘
鈴木さんによる「若手からの問題提起」は、ERM委員会の若手メンバーを中心とした意見交換の内容に基づいています。
業務負担が年々増えて現場が疲弊しているとか、形を整えることばかりに固執して、有効に機能するリスク管理になっていないとか、考えさせることばかり。
なかには、「(当局に報告する)ORSAレポートに載せたいから、この数字を計算してほしい」「数字が大きくぶれるのは計算方法が悪いから」「ストレステストの結果が悪かったので、シナリオを見直すべき」といった、耳を疑うような「証言」も出ました。
当日は双方向ツールを使って参加者アンケートを行っています。最初のほうでストレステストやORSAについて聞いたところ、やはり「報告やレポート作成自体が目的化し、あまり活用できていない」が4択のうち6割以上の回答を集めました。
なぜ「リスク文化」が選ばれたのか
参加者アンケートは最後のほうでも行いました。「今のリスク管理に足りないもの、強化していくべきものは何か?」という質問に対し、
リスク文化 55%
ガバナンス 31%
PDCAサイクル 11%
ツール 2%
外部の関与 1%
と、過半数のかたが「リスク文化」を選んでいます。直前で私が「ガバナンスのところを何とかしないと、せっかくERMの枠組みを作っても、魂が入らない」と熱く(?)語っていますね^^;
当日は進行役の市川さんが、「ツール以上に文化やガバナンスが大事だと皆さんも感じていただけた」とうまくまとめていましたが、この結果をどう捉えるべきか。
若手の実務担当者として、「あるべきリスク文化は自分たちが率先して築いていかなければならない」という表明だったらいいのですが、もしかしたら、「今のままでは意味のない(と思えるような)作業ばかりで、上司や周囲の考えが変わらなければ何も変わらない」という諦めの心境の現れなのかもしれません。
いずれにしても、どこかで「リスク文化」を深掘りするような機会があるとよさそうです。
パネルディスカッションの詳細はこちらをご覧ください。
※浅草のこの展望台には初めて行きました。
スカイツリーもよく見えます。

※いつものように個人的なコメントということでお願いします。
ブログを読んで面白かった方、なるほどと思った方はクリックして下さい。