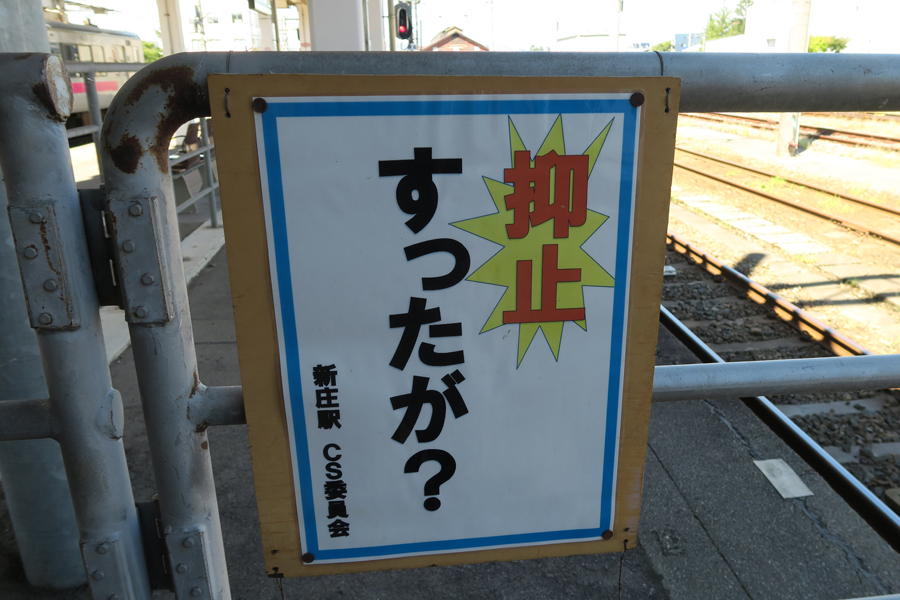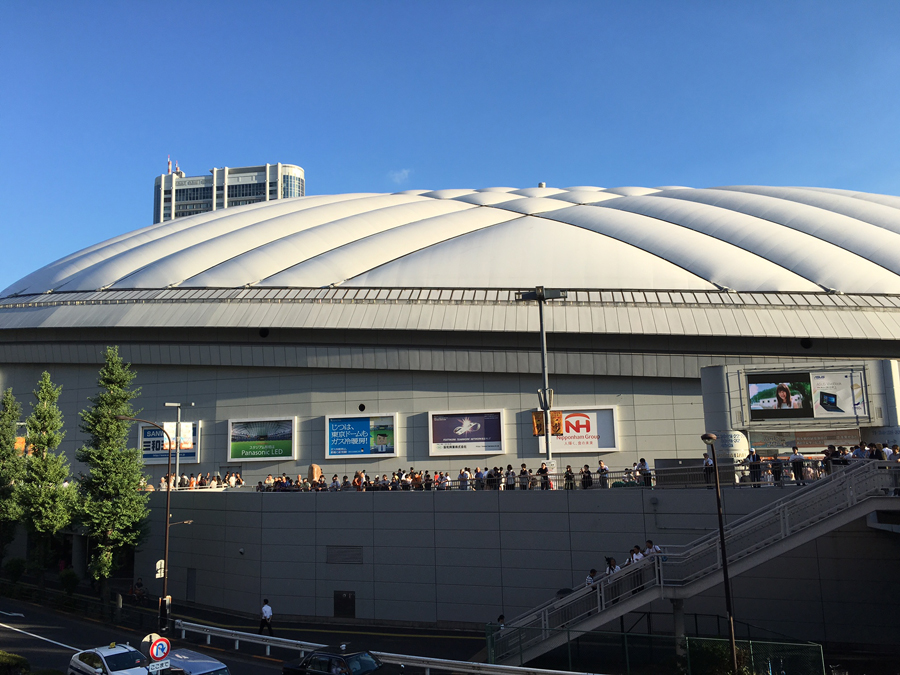バイタルデータ(生体情報)、すなわち、BMIや血圧、
コレステロールといった健康状態に関連する指標を
使った保険商品・サービスが注目されています。
20日には、第一生命グループの一員である
ネオファースト生命が「健康年齢」を活用した
生活習慣病保険を12月に発売すると発表しました。
ネオファースト生命のサイトへ
ノーリツ鋼機グループの日本医療データセンターが
保有する約160万人の健診データ等の医療情報を
もとに健康年齢を判定し、更新時の保険料を決める
という仕組みです。
日本データ医療センターの医療情報を保険料算出に
活用した商品は、すでにノーリツグループが設立した
健康年齢少額短期保険会社で販売されています。
健康年齢少短保険のサイトへ
1年更新の医療保険で、5大生活習慣病(がん、
脳卒中、心筋梗塞、高血圧、糖尿病)で入院したら
80万円の給付金を受け取れるというものです。
毎年、「健康年齢」を算出し、保険料が決まります
(ネオファースト生命の「健康年齢」とは別の基準)。
試しに健診データを入力してみたところ、
実年齢よりかなり若い結果が出て、思わずニッコリ。
ただ、考えてみれば、どうしてこの健康年齢に
判定されたのか、〇歳という総合評価だけなので、
見当がつきません。
これまでのバイタルデータを使った保険では、
例えば「ノンスモーカーかどうか」などのように、
ある程度の納得感がある指標で割引が決まります。
これに対し、「健康状態が良好であれば、保険料が
安くなる(または、割引がある)」のはわかるものの、
何となくブラックボックス感が強いという印象です。
総合評価だけでなく、判定についての説明があると
いいのかもしれませんね。
更新時までの生活の参考になるかもしれません。
あるいは、健康年齢が低いと生活習慣病に
どの程度かかりにくいのかというデータを示すのも
一案ではないでしょうか。
リスク細分型の保険では、もちろん、信頼できる
客観的な指標を使うことが大前提ですが、
それをどう示し、顧客にいかに納得してもらうかも
普及のカギとなるように思います。
※写真は金山の大堰と小学校です。
※いつものように個人的なコメントということでお願いします。
ブログを読んで面白かった方、なるほどと思った方はクリックして下さい。