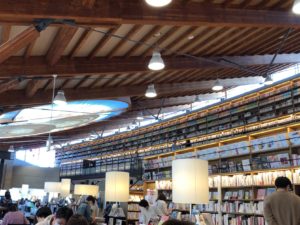3月31日に第一生命ホールディングスが新たな中期経営計画を公表しました。
メディアで報道されたのは主に「元営業職員の金銭詐取事件(=第一生命が全額補償すると同じ日に公表)」のほうでしたし、株式市場では自己株式取得(=上限2000億円の取得を決定)が好感された模様ですが、新中計の中身も注目に値するものだと思います。
第一生命HDのサイトへ
これまでの中計は、つまるところ「グループ修正利益(=会計ベース)をいかに高めるか」を最も重視していたように見えました。もちろん、生保事業の新契約価値を高める取り組みも行ってきているのですが、こちらはグループ修正利益をただちに増やす効果はないので、外国証券の利息配当金を増やすなど、修正利益への即効性の高い資産運用に依存することとなり、結果として金融市場の変動に左右されやすいリスクプロファイルがずっと変わりませんでした。
これに対し、新中計は「ありたい自分」を見据えたうえで策定され、重要経営指標(KPI)は利益の絶対額ではなく、資本効率やリスク削減目標など、企業価値や資本コストを強く意識した、これまでにないものとなりました。グループ修正利益の絶対額は想定レンジを置いただけです
(事業規模の指標としては「お客さま数」を掲げています)。
資本充足率(ESR)のターゲット水準に加え、資本政策の考え方も示しました。
競合する大手他社が総じて保険料や基礎利益を目標とするなかで、今回の第一生命グループの新中計は経営の変化を感じさせるものでした。あとは、株主やメディアなど外部ステークホルダーの理解を得るために、説明を重ねていく必要があるのでしょうね。
<参考>
日本生命グループの中計(2021-2023)のKPI
・お客様数(国内)
・保有年換算保険料(国内)
・基礎利益(グループ)
・自己資本(グループ)
住友生命グループの中計(2020-2022)のKPI
・保有契約件数(国内)
・保有契約年換算保険料(国内)
・うち生前給付保障+医療保障等(国内)
・基礎利益(国内)
・基礎利益(海外)
※福岡の桜はほぼ散ってしまいましたが、せっかくなので先週の写真を。

※いつものように個人的なコメントということでお願いします。
ブログを読んで面白かった方、なるほどと思った方はクリックして下さい。