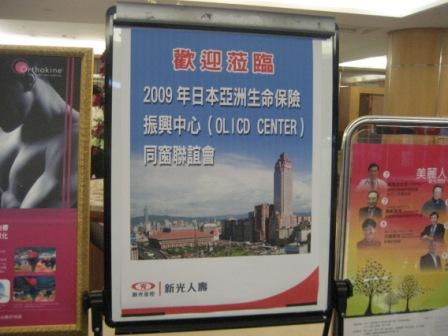昨日(7/29)、損保ジャパンと日本興亜損保が「経営統合に向けての契約書」
を締結し、経営統合計画の概要を発表しました。
この件で、30日の日経に私のコメントが載っています。
「損保ジャパンの株主から統合を評価されるには、新会社が
どう将来利益を生み出していくかの明確な事業計画が必要」
というものです。
コメントの内容はおかしくないと思うのですが、そもそも、
株主でも株式アナリストでもない私がコメントするのは変な話です。
ただ、大株主はこのタイミングでコメントするわけにはいかないでしょうし、
株式アナリストはレポートを出す前に見解を話せないのでしょう。
そのような背景があるということでご理解下さい。
7/27号の日経ビジネス「統合比率は1対0.9 !?」という記事にも
コメントが出ています。同じような事情があるのだと思います。
ちなみにコメントは、
「サブプライムローン関連の証券化商品を含む金融商品の保証をする
金融保証保険で2009年3月期に1479億円もの損失を出した」
というものです。ただ、そのあとに
「このため、統合比率は日本興亜側に有利になる可能性もある」
と続いています。私自身は統合比率についてコメントしていません。
このあたりは対応がなかなか難しいところです。
発表当日は記者会見のほか、機関投資家・アナリスト向けカンファレンス
(≒電話&ネット会議)が開催されました。
私は投資家向けカンファレンスにアクセスしましたが、統合比率に関しては、
「確かに1株当たり純資産のような指標で見ると差があるかもしれないが、
統合によるシナジーが見込めるので、損保ジャパンの株主にも
十分メリットがあるはず」
というコメント(質問に対する回答)がありました。
株主の理解を得られるかどうか、年末の臨時株主総会に注目です。
他方、記者会見では「統合効果は消費者にも還元されるのか」といった
カンファレンスとはかなり違うやり取りがなされたようです。
※いつものことですが、写真と本文は関係ありません。念のため。
※いつものように個人的なコメントということでお願いします。
ブログを読んで面白かった方、なるほどと思った方はクリックして下さい。





.jpg)


.jpg)