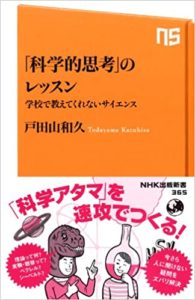今週のInswatch Vol.1144(2022.7.11)に記事を寄稿しました。こちらでもご紹介いたします。
——————————
今年も台風の季節になりました。2018年度や19年度のような大規模な自然災害が発生しないことを願っています。
火災保険は赤字基調が続く
昨年度(21年度)の大手損害保険グループの決算は、自然災害関連の正味支払額が過去10年間で最も少ない水準だったこともあり、国内損保事業の修正利益(異常危険準備金の繰入・戻入などを調整した利益)はいずれも増益となりました。
もっとも、自然災害による支払いが少なかったにもかかわらず、火災保険のコンバインドレシオが100%を下回ったのは東京海上日動だけで、他の3社は引き続き100%を上回る水準でした。大手損害保険会社はこれまで少なくとも2回にわたり個人向け火災保険の料率引き上げを行いましたが、大規模な自然災害がなくても火災保険の収支はなお赤字基調ということで、さらなる対応が必要な状況です。
21年度の保険会社の決算分析については、今月末のプロフェッショナルレポートでもお伝えする予定です。
損保ビジネスは不安定なのか
ところで損害保険ビジネスは、自然災害に左右される不安定なものと思われがちです。過去の決算報道を見ても、大規模な自然災害が発生しなければ「好決算」、発生したら「厳しい決算」という扱いです。しかし、本当にそう考えるべきなのでしょうか。
保険会社は自然災害リスクを勘と度胸で引き受けているのではありません。工学的な知見に基づき、外部ベンダーまたは自社が開発したモデルを使った定量的なリスク評価を行い、再保険戦略を含めた引受方針を定めたうえで、自然災害リスクを引き受けています。気候変動の影響が懸念されるとはいえ、やみくもにリスクを引き受けているわけではありません。
ですから、自ら決めたリスクの引受方針次第で、同じ自然災害が発生しても正味支払額は違ってきます。例えば、過去最高の支払額となった18年度決算において、損保ジャパンでは自然災害に伴う元受保険金の約7割を再保険で回収したのに対し、東京海上日動では約3割の回収だったため、両社の支払額が元受ベースと正味ベースで逆転していました(東京海上の正味支払額が大きかった)。だからといって、東京海上日動がリスク管理に失敗したとは言えません。ここからわかるのは両社の保有・出再戦略が異なっていたというだけで、中長期的に見て、各社がリスクに応じた保険料(出再コストを含む)を獲得できているかを把握しなければ、各社のパフォーマンスを評価できません。
リスク情報の開示を
ただし、再保険に関して言えば、両社の保有・出再戦略にここまで違いがあるとわかったのは、たまたま18年度と19年度に大規模な自然災害が発生したからであって、それ以前の開示情報だけでは外部からはわかりませんでした。再保険に限らず、外部ステークホルダーにとって、リスク引受方針をはじめ、リスクに応じた保険料を獲得できているかをつかむための手掛かりは、まだまだ少ないのが現状です。
もし損害保険会社の経営陣が外部から正当に評価されたいと考えているのであれば、より踏み込んだリスク関連情報の開示が必要だと思います。
——————————
※写真は三角西港です。明治時代の港がそのまま残っています。

※いつものように個人的なコメントということでお願いします。
ブログを読んで面白かった方、なるほどと思った方はクリックして下さい。