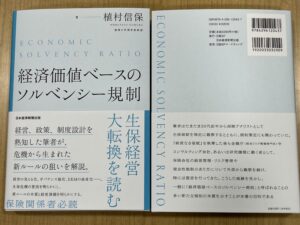1つの政党を除き、どの政党も公約に消費減税(検討を含む)を掲げるとは…
消費税を廃止するというのは、例えば年収300万円(同額を消費)の家計に30万円弱を配るというだけでなく、年収1000万円(うち500万円を消費)の家計にも50万円弱を配るという政策ですし、食料品の消費税をなくすというのは、年収300万円(食料品への消費が100万円)の家計だけではなく、年収1000万円(同100万円)の家計にも約8万円を配布するという政策ですよね。物価高対策として悪手としか思えません。
とはいえ皆さん、選挙には行きましょう。究極の消去法だとしても、意思表示は必要です。
さて、1月23日のBloombergに「金融庁が大手生保の債券含み損など調査、金利上昇受けて-関係者」というニュースが出ていました。31日の日経にも「金利急騰に苦慮の金融庁、生保に矛先 ダボス帰りの片山財務相発端に(会員限定記事)」というのがありました。
いずれの記事も、金融庁が1月中旬から生保(まずは大手4社)の保有する国債などの含み損益やその対応方針について調査を行っているという内容でした。
金利が上昇すれば保有する債券の価格は下がります。例えば、2019年発行で利率0.4%の30年国債の価格は直近で50円近くまで下がっていますし、利率0.5%の40年国債の価格は40円近くまで下がっています。今月半ばに発表される生保の2025年4-12月期決算では、9月末よりも各社の含み損が拡大していることでしょう。
ただし、生保が長期債を保有しているのは、同じく長期にわたる保険負債の金利リスクをヘッジするためなので、資産サイドの保有債券だけに注目しても意味はありません。ましてや、この3月末から経済価値ベースの評価による貸借対照表と、それに基づく数値基準(規制ESR)による規制を始めるのですから、政府は監視強化ではなく、むしろ会計上の評価に神経質となっている保険会社を安心させるべきでしょう(解約動向はよく確認する必要があると思いますが)。
Bloombergの記事で気になったのは、「金利上昇により過去に購入した保有国債の含み損は膨らんでおり、財務の健全性を示す指標の悪化につながりかねないとの警戒感はすでに生保側からも出ている」というところです。
ここで言う「財務の健全性を示す指標」とは何を指すのでしょうか。規制ESRのことだとしたら、保有国債の含み損は関係ありません。保険負債も小さくなっているはずなので、純資産はむしろ膨らんでいるはず。
負債の金利リスクをフルヘッジしていないにもかかわらず、金利上昇でESRが下がるのは、大量解約リスクという、いわば流動性リスクを数値化してしまったことによる影響でしょう。
日経記事にも「低金利時代に国債を買い増したことが含み損の拡大につながり『規制対応が裏目に出ている』(生保幹部)面もあり、場当たり的な監視強化に戸惑いもある」とあります。場当たり的と言わせないよう、金融庁は対話と情報発信をがんばってほしいですね。
※梅の季節になりました。横浜・大倉山の梅林にて。

※いつものように個人的なコメントということでお願いします。
ブログを読んで面白かった方、なるほどと思った方はクリックして下さい。