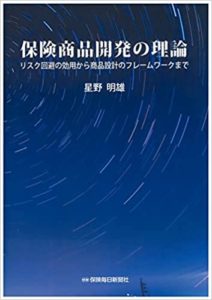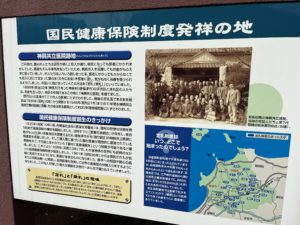昨年11月28日のブログと同じように、公表された大手生保の資産運用実績を、10月下旬に各社が特定メディアに説明した資産運用計画と比べてみました。概ね説明通りの実績となっているように思います。
【日本生命】
「2021年度下期の一般勘定資産の運用方針では、海外の社債などクレジット資産を中心に投資する計画だ。米国債や日本の超長期債への投資は足元の金利水準が魅力的ではないとして慎重な姿勢を崩していない」(10月26日ロイター)
⇒
クレジット資産かどうかはわかりませんが、9月末と12月末を比べると、外国公社債と外国株式等が増えています。
責任準備金対応債券区分の残高が増えているので、「魅力がない」とする日本の超長期債もおそらく購入が続いているのではないでしょうか。1-3月の動向に注目です。
【第一生命】
「円建て債券は責任準備金対応債券の積み増しにより残高を増やす一方、国内株式はリスクコントロールのため売却する。外貨建て債券については、金利や為替の水準次第だが、足元の水準程度での推移であれば残高の大きな増減は見込んでいない」(10月26日ロイター)
⇒
計画の通り、引き続き国内公社債を増やし、国内株式を減らしています。HDのIR資料によると、資産デュレーションは9月末の17.5年から12月末は17.6年と、やや伸ばしたといったところでしょうか。
外国公社債の残高はそこそこ減っているようです。IR資料に「外貨建債券運用の状況」という開示があり(今回が初めてでしょうか?)、外貨建債券の約80%が為替ヘッジ付きだそうです。
今さらですが、プロテクティブの確定利付き資産は、BBB格以下が46%を占めているのですね。
【住友生命】
「長引く低金利環境でのリターン確保を目指し、為替リスクをヘッジしないオープン外債を数千億円規模で積み増すほか、外部委託での海外クレジット投資にも力を入れる方針を示した。一方、国内債券は25年の経済価値ベースの資本規制導入を前に金利リスクを削減するため、超長期国債をメインに1000億円程度積み増す方針」(10月26日ロイター)
⇒
為替ヘッジ状況の手掛かりはありませんが、確かに外国公社債が9月末に比べて2000億円以上増えています。外国株式等も増えていて、「外部委託での海外クレジット投資」がここに含まれるのでしょうか。
国内公社債はそれほど増えていないように見えます。
【明治安田生命】
「25年の経済価値ベースの資本規制導入に向けて、円建て債券の積み増しや国内株式の売却によりリスク低減を図る一方、総合的な利回り確保のために外貨建てクレジット資産や外国投信などへの投資にも積極的に取り組む方針を公表した」(10月25日ロイター)
⇒
12月末時点では、国内株式の売却はあまり進んでいないように見えますが、責任準備金対応債券区分の残高は引き続き増えています。外国公社債や外国株式等が増えていて、クレジット資産や外国投信に積極的に取り組んだ結果なのかもしれません。
【かんぽ生命】
「円金利資産は総資産が縮小する見込みのため残高を減らす一方、国内株式やオルタナティブ資産を積み増す計画を示した。外貨建て債券については、為替ヘッジ付き・オープンともに残高は横ばいを見込むが、特にオープン外債には慎重な姿勢を見せた」(10月27日)
⇒
総資産が3か月で1兆円ほど減るなかで、確かに国内株式や外国株式等は増えていますし、IR資料からも内外株式とオルタナ投資の増加が確認できます。
資産が減っているのは旧区分だけではなく、新区分も減っているのですね。
※終着駅シリーズ。北九州の若松駅です。

※いつものように個人的なコメントということでお願いします。
ブログを読んで面白かった方、なるほどと思った方はクリックして下さい。