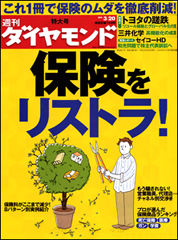首都ハノイとホーチミンを結ぶベトナム国鉄に乗ってみました。
フエからダナンまで約100kmの旅です。
ベトナムの鉄道はお世辞にも発達しているとは言えません。
ハノイとホーチミンを結ぶ最重要路線でも1日5便しかなく、
単線・非電化で、最速30時間近くもかかります。
しかも車内の設備はかなり老朽化しています。
ただ、ツーリストにとっては旅情満点。懐かしの汽車旅を楽しめました。
特に私が乗った区間は海岸近くの峠を超える絶景コースだったので、
多くの旅行者が車窓の景色を満喫していました。
時間もかなり正確でしたし、乗務員も多く、安心です。
乗客どうしの交流もあります。
同じコンパートメントのベトナム人カップルは新婚さんで、
ハネムーンでビーチリゾートに行く途中とか。
京都の高校で英語を教えている2人のアメリカ人とも
日本語&英語で話すことができました。
日本で新幹線に乗っても、隣の人に話しかけたりしないですよね。


ベトナムでも高速鉄道を作る計画があるそうです。
日本の新幹線を導入する可能性が高いとか。
完成すればかなりのスピードアップになるはずで、
おそらくハノイ・ホーチミン間は10時間以内でしょう。
資金面の問題は大きいようですが、在来線の改良では
限界があるように感じました。
※いつものように個人的なコメントということでお願いします。
ブログを読んで面白かった方、なるほどと思った方はクリックして下さい。