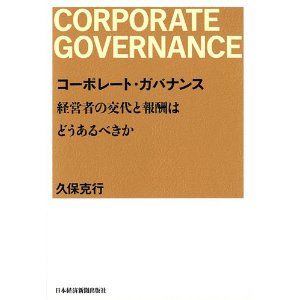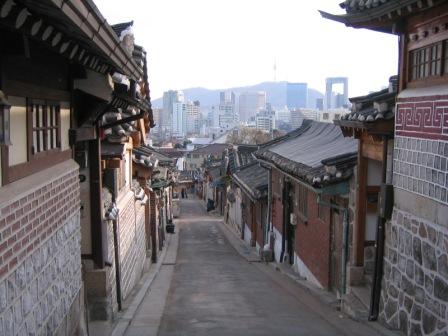2008年の金融危機を受けて販売休止が相次いだこともあり、
2009年度は変額年金の販売が減少し、銀行窓販の主力が
定額商品(定額年金、一時払い終身保険)に移りました。
これは日本の話です。
米国ではどうなっているのか気になったので調べてみると、
変額年金の販売はやはり2008年、2009年と減っています
(LIMRAのHPより)。
ただ、2008年に急増した定額年金の販売が、2009年には
小幅ながら減少しているところをみると、必ずしも変額年金から
定額年金にシフトしているわけではないことがうかがえます。
しかも、2010年の1-3月には変額年金の販売が前年を上回りました。
なぜ日本とは異なる動きになるのかというと、
一つは販売チャネルの違いがありそうです。
日本では銀行が一時払い商品のメインチャネルとなっており、
変額/定額ともに銀行が販売しています。
他方、米国では主に銀行が定額年金を販売し、
変額年金は証券チャネルが積極的に扱う、というとやや言いすぎですが、
証券チャネルの存在が大きいのは間違いなさそうです
(他に年金制度の違いも大きいようですが、ここでは触れません)。
もっとも、米国でも販売上位の顔ぶれは変わっています。
変額年金ではプルデンシャル、メットライフの2大生保が上位を占め、
INGやハートフォードは順位を下げています。
AIGは変額年金で7位、定額年金で2位と善戦しているようです。
※保険会社の本社は風格のあるビルが多いですね
(どこだかわかりますか?)。
※いつものように個人的なコメントということでお願いします。
ブログを読んで面白かった方、なるほどと思った方はクリックして下さい。