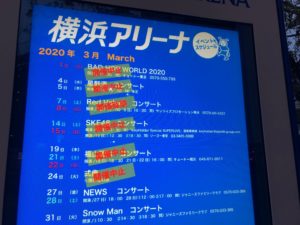福岡に赴任してから初めての週末とはいえ、こちらでも外出自粛の要請が出ていますので、自宅近くを買い物がてら散歩するくらいしかできません。それでも歩いて10分くらいの福岡城址は桜が満開で、見事な眺めでした。

業績も募集品質も良い募集人にヒアリング
3月26日に公表された「かんぽ生命保険契約問題 特別調査委員会 追加報告書」を遅まきながら確認したところ、「優良な募集人の共通点」なる分析が載っていました。
調査委員会では、昨年度の年間販売実績額が500万円以上で、かつ、募集品質データ上、撤回・未入金解除等の発生率、乗換潜脱発生率及び料済・減額発生率のいずれの数値も低く、さらに、3 年間の契約保有率が良好な募集人を対象にヒアリングを実施したそうです。
共通点は以下のとおりです。
(1) 常日頃から、保険の知識のみならず、それ以外の分野についても幅広く勉強を続けるなど、顧客にかんぽ生命保険の保険商品を勧奨する際に役立つ知識や経験を得るために、創意工夫を重ねていた
(2) 顧客のニーズに合致した保険商品を提案できるよう、顧客を訪問する際には事前に顧客の状況を入念に調べた上で赴いていた
(3) 既契約者である高齢者のみならず、かんぽ生命の保険商品に加入したことのない青壮年層をも広く募集の対象としていた
(4) 飛び込み営業も含めて顧客への訪問を多数かつ多頻度で行っており、一般の募集人よりも活動量が多かった
(5) 活動量の多さに加えて、自らが契約を受理した顧客から、とりわけ青壮年層の家族、友人等の紹介を受けることを通じて新規顧客を増やしていくことが多かった
(6) 顧客に対して募集を行う際は、顧客の話をよく聴き、顧客のニーズを把握した上で、そのニーズに合致する保険商品を提案することを心掛けていた。また、顧客に対して保険商品の提案を行った後は、最終的にその保険に加入するかどうかは顧客の判断に委ねることで、加入する保険が顧客ニーズに合致するよう留意していた
(7) かんぽ生命保険商品の商品性の魅力が乏しいことは、販売実績を挙げて営業目標を達成する上での障壁にはならないと考えていた
(8) 顧客が保険に加入した後は、自筆で御礼状を書いて送るなどの丁寧なアフターフォローを行っていた
報告書には、それぞれに関する募集人ヒアリングからの引用も載っていますが、本来は個々の募集人のがんばりに頼るのではなく、組織として営業というものをどう考えていくかという話なのでしょう。
そうした意味で参考になるかどうかはわかりませんが、一読をお勧めします。

※いつものように個人的なコメントということでお願いします。
ブログを読んで面白かった方、なるほどと思った方はクリックして下さい。