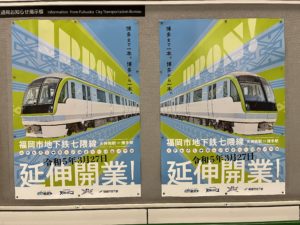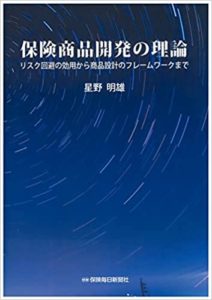保険代理店向けメールマガジンInswatch Vol.1252(2024.10.14)に寄稿した記事を当ブログでもご紹介いたします。今回は大学の講義(保険論など)の一部をご紹介します。
3連休が多いので、月曜日の授業は遅れがちです。
————————————
根強い「掛け捨ては損」という考え
大学の講義のなかで、次のような質問をすることがあります。保険のプロである皆さんには釈迦に説法で恐縮ですが、どうかお付き合いください。
【どちらのほうが経済的に得でしょうか?(保険会社は1も2も同じ)】
1.いわゆる「掛け捨て」の定期保険
死亡保険金額:1000万円
保険期間:10年
毎月の保険料:1000円(20歳加入)
2.死亡しなかったら「お祝い金」がもらえる保険
死亡保険金額:1000万円
保険期間:10年
毎月の保険料:6000円(20歳加入)
お祝い金:60万円(死亡しなかった場合)
当然ながら正解は1です。それでも「2のほうが得」「1と2は経済的に同じ」と答える学生が相当数います。
お祝い金の原資は保険料
念のため、1のほうが経済的に得である理由を説明しておきましょう。
同じ保険会社なので、2は1の定期保険に貯蓄機能が加わったものと考えられます。毎月の保険料6000円のうち、1000円が定期保険の保険料で、5000円が貯蓄に回ります。保険期間の10年は120か月なので、5000円×120=60万円という計算になります。
ただし、お祝い金がもらえるのは「死亡しなかった場合」です。保険期間中に死亡したら、死亡保険金1000万円は受け取れますが、毎月の保険料から貯蓄に回っていたはずのお金は返ってきません。
では、死亡した場合にも「おくやみ金」として貯蓄部分を受け取れるとしたらどうでしょうか。それでも1のほうが経済的に得です。
2と比べやすくするため、1の保険に加入するとともに、毎月5000円を銀行に預けるとしましょう。1では、わずかですが預金利息が付くので、10年後の預金残高は60万円を超えます。
理由はそれだけではありません。1の銀行預金はいつでも貯まっている分を使うことができます。でも、2の貯蓄部分は10年経たないと受け取ることができません。貯蓄といっても自由に使えないお金です。
2の保険加入では、いわば強制的にお金を貯めることができるとはいえ、果たして経済的なデメリットを上回るほどの効用があるでしょうか。
顧客本位なのか
今回お示ししたのは定期保険(死亡保険)の例で、かつ「お祝い金」が経済的にみて低く設定されていました。しかし、お祝い金を経済合理的に設定したとしても、死亡保険よりも給付金額の小さい医療保険では、より悩ましい問題が起こり得ます(給付金を受け取るとお祝い金がもらえない場合)。
というのも、給付金とお祝い金を天秤にかけ、場合によっては給付金の請求をしないほうが多くの金額を受け取ることができるからです。こうなってくると、そもそも何のために医療保険に加入したのか、よくわからなくなってきます。
もしかしたら、お祝い金のある保険のほうが経済的に得となる料率設定をしている会社があるのかもしれません。とはいえ、それを比較検討するのは至難の業です。そうだとすると、いくら顧客ニーズが強いからといっても、この手の商品を勧めるのが顧客本位とは考えにくいですね。
————————————
※日田彦山線BRTに乗りました。

※いつものように個人的なコメントということでお願いします。
ブログを読んで面白かった方、なるほどと思った方はクリックして下さい。