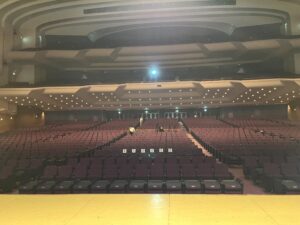最初にご案内です。2021年に出版した『利用者と提供者の視点で学ぶ 保険の教科書』(中央経済社)の第2版が出ました。アマゾンだと20日から取り扱いのようです。
第2版では図表を直近データに更新しただけではなく、国内金利の上昇を踏まえた記述にしたり、損害保険業界の「保険金不正請求事件」と「保険料カルテル問題」を取り上げたりしています。入門書として読みやすさを優先した『保険ビジネス』では少し物足りないかたや、保険について体系的に学びたいかたは、ぜひ本書をご覧ください。
ところで、生命保険協会は統計資料として会員各社の主要業績を取りまとめていて、全社合計データをサイトで公表しています。このうち年次統計の「新契約年換算保険料(ANP)」では、「個人保険」「個人年金保険」「第三分野」それぞれの内訳や、払込方法別(平準払/一時払)、通貨別(円/米ドル/ユーロ/豪ドル/その他)のデータも公表しています。
さらに、協会では年次統計のCDを「生命保険事業概況」として外部に提供していて、こちらには同じデータが会社別にも載っています。
年末に入手した2024年度版をもとに、新型コロナ禍直前の2019年度から2024年度までの新契約ANPを眺めてみたところ、近年の生保市場の変化が見えてきました。以下、いくつかご紹介しましょう。
まず、全社合計の新契約ANPは、コロナ禍の落ち込みを乗り越え、2024年度は2019年度の約1.3倍に拡大しました。ただし、平準払はほぼ横ばいで、増えたのは一時払です。
新契約ANP 1.93兆円 ⇒ 2.56兆円
平準払 1.36兆円 ⇒ 1.37兆円
一時払 0.57兆円 ⇒ 1.18兆円
平準払は全体的に低調で、第1分野は変額保険を除くと減少。第3分野も2019年度の水準を下回っています。
他方、一時払の販売拡大の牽引役は円建です。2024年度は円建のANPが外貨建に匹敵する水準となりました。残念ながら半期データは公表されていないのですが、おそらく傾向は変わっていないと思います。
会社別データも興味深いです。例えば大手4社(日本、第一、住友、明治安田)の新契約ANP、うち一時払とその割合は次のとおりです(2024年度)。
日本 2339億円/562億円(19.6%)
第一 959億円/-(-%)
住友 962億円/549億円(57.1%)
MY 1261億円/524億円(41.5%)
これだと、一時払を提供していない第一生命と、新契約ANPに占める一時払の割合が4、5割もある住友生命、明治安田生命の数字を単純に比べても、あまり意味を成さないということになりますね。ちなみに、住友生命の一時払は円建が目立つのに対し、明治安田生命は外貨建が中心でした。
損保系生保3社(あんしん、MSA、ひまわり)では、一時払や外貨建をほとんど提供していない点は共通していましたが、平準払の内訳は結構違っていました。あんしん生命はこの5年間に、新契約ANPの中核が第3分野から変額保険に変わりました。MSA生命は第3分野が減少する一方で変額以外の第1分野を伸ばし、ひまわり生命は第3分野とともに変額保険にも注力しているようです。
もっとも、あと2か月ほどで2025年度が終わるという時期なので、やや古い情報ではあります。
各社が決算発表の際、あるいはディスクロージャー誌でこの情報を出してくれるといいのですが。
※写真は東京・日本橋です。

※いつものように個人的なコメントということでお願いします。
ブログを読んで面白かった方、なるほどと思った方はクリックして下さい。