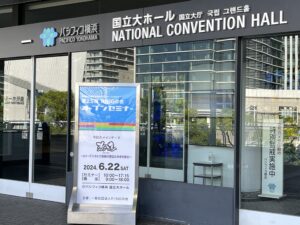12月24日に金融審議会「損害保険業等に関する制度等ワーキング・グループ」報告書が公表されました。
すでに12月10日のブログ「損保WG報告書案が判明」で触れているので、それとは別の観点から2つコメントします。
1つは保険業法だけではなく、「改正金サ法」(2023年に改正された「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」)や「顧客本位の業務運営に関する原則」に関する記述が盛り込まれていることです。
金融審の市場WGでは主に家計における資産形成を念頭に議論が進められ、実際、WGのオブザーバーに損害保険関係の業界団体は入っていませんでした。しかし、今回の報告書を読むと、「保険募集人全般においてもその(=顧客本位の業務運営の)定着が望まれるところであるが(後略)」「改正金サ法により、保険募集人を含む全ての金融サービス提供事業者に対し、顧客等の最善の利益を勘案して誠実かつ公正に業務を遂行する義務が明記されたことも踏まえ(後略)」と、損害保険代理店でも顧客本位原則の採択が当然視されています。
もう1つは、火災保険の赤字構造の改善等のところで、リスクに応じた適切な保険料の設定等が確保されるための態勢をモニタリングしていくとあるのですが、報告書ではそもそも「あるべき姿」としてどのような態勢を念頭に置いているのか気になりました。
21ページの注記には、モニタリング高度化の具体例としていくつか書いてありますが、かなり漠然とした内容です。第1線の営業部門・業務部門による引受規律を期待しているのか、あるいは第2線のリスク管理部門の機能に期待しているのかなども気になりますし、リスクベース・プライシングなのに「資本コスト」「再保険」といった記述が出てこないのも不思議です。
さらに言えば、仮に態勢ができていたとしても、実行されているかどうかを外部からモニタリングするには、かなりの専門性が必要となるように思います。
※今年は飛行機によく乗りました。

※いつものように個人的なコメントということでお願いします。
ブログを読んで面白かった方、なるほどと思った方はクリックして下さい。