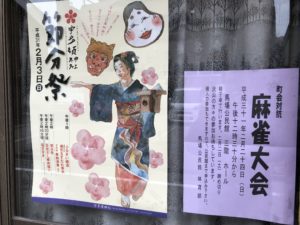3月期末の30年国債利回りは0.507%と、マイナス金利政策の開始直後だった2016年3月末(0.547%)よりも低い水準でした。厳しいですね。
生保への副作用も大きい
長引く異次元緩和の副作用として銀行経営への悪影響が注目されていますが、生保経営へのインパクトも、現行会計では見えにくいだけで、非常に大きいものがあります。
ソルベンシーマージン比率が高水準にもかかわらず、劣後調達が相次いでいるのを見ても、厳しさの一端がうかがえます。
商品面への影響も大きく、これだけ金利水準が下がってしまうと、円建ての貯蓄性商品の提供は実質的にできません。そこで保険会社が注力してきたのが外貨建ての貯蓄性商品であり、販売休止となった経営者向け保険であったと言えるかもしれません
(もちろん、他にも健康増進型保険など個人向けの保障性商品への新たな取り組みもあります)。
ちなみに金融庁は2月に行われた生命保険協会との意見交換会で、「低金利環境による厳しい収益環境が続いているとはいえ、トップライン維持のために、過去を反省することなく、このように法令や監督指針に照らして問題がある商品まで投入してしまうという保険会社の姿勢はいかがなものか。経営の在り方としてはあまり美しくないと感じざるを得ない」という異例のコメントをした模様です。
経営者保険の保険料は個人保険の3割程度
経営者向け保険が販売休止となったことによる生保経営への影響を考えてみましょう。
最近出た東洋経済オンラインの記事によると、経営者向け保険の推定市場規模は新契約年換算保険料ベースで8000億~9000億円とのこと。
「経営者向け保険」「法人向け定期保険」といった統計はありませんが、個人で保険料を年払いにしている人は少ないと考えられますので、公表されている年払保険料を見ると大まかな傾向をつかむことができます。
2018/3期における個人保険の初年度保険料のうち、年払いは業界全体で8662億円でした。異次元緩和が始まる直前の2013/3期と比べると2160億円、マイナス金利直後の2016/3期と比べても985億円増えていて、内訳を見ると、2つの大手生保グループが大きく寄与しています。
個人保険全体に占める割合をざくっと見ると、新契約年換算保険料と比べて39%、初年度保険料(振れの大きい一時払いを除く)と比べると34%です。
個人向け商品の年間保険料に比べ、経営者向けの1件あたりの保険料が高いので、件数としては全体の1割未満だとしても、保険料収入でみると割合が高くなります。
ちなみに2013/3期はそれぞれ31%/29%、2016/3期はそれぞれ32%/31%だったので、割合は高まっています。
経営への影響をどう見るか
ただし、経営者向け保険の競争が激しかったためか、保障性商品に比べると収益性はかなり低いとみられます。
第一生命ホールディングスによると、第3四半期累計(2018/4-12)の国内3社の新契約年換算保険料3150億円のうち、販売休止となった商品が950億円と、全体の30%を占めたそうですが、新契約価値については年100~200億円程度にとどまるそうです(参考までに2018/3期の新契約価値は3社合計で1651億円でした)。
手掛かりが少なく正確なところはわかりませんが、大手生保のように個人も法人も手掛けている会社では、少なくともこの要因だけで新契約価値が急減することは考えにくいです。
もっとも、個社別に見ると、年払い保険料が初年度保険料(除く一時払い)の7割以上を占める会社がいくつかあり、営業戦略の大幅な見直しを迫られていると考えられます。
同じくこの分野に強みを持ち、節税話法に傾斜していた訪問型代理店への影響も深刻でしょう。
わかっていたリスクがこのタイミングで顕在化したという話ではありますが…
※写真は秩父です。電車はさくら号でも、咲いていたのは梅でした^^

※いつものように個人的なコメントということでお願いします。
ブログを読んで面白かった方、なるほどと思った方はクリックして下さい。