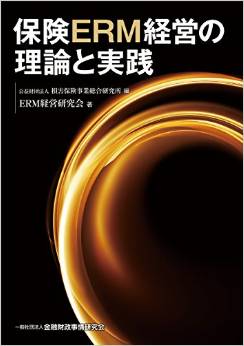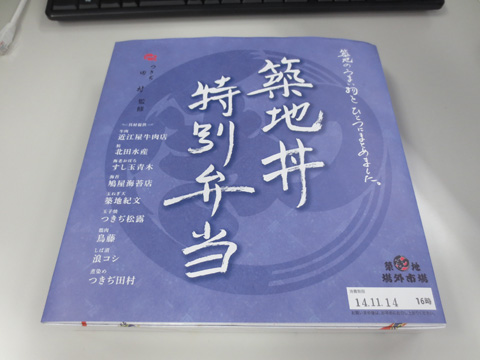あけましておめでとうございます。
いいお正月休みを過ごされたでしょうか。
私は原稿書きに追われる年末年始となってしまい、
先ほど紅白のDVDをダイジェストで観ました(笑)
新年最初のブログは保険ネタではなく、
年末に訪れた富山の話です。
富山市は「コンパクトシティ構想」と言われる
中心市街地の活性化に取り組む市として有名で、
そこでは鉄軌道網をフル活用しています。
トラム好きにもかかわらず訪れる機会がなく、
このたび短時間ながらようやく実現しました。
富山市の「公共交通を軸とした拠点集中型の
コンパクトなまちづくり」の詳細はこちらをご覧下さい。
現在のところ、富山駅の高架化とともに廃止も
検討されたJR富山港線のライトレール化
(市街地は路面を走り、郊外は普通の電車に)と、
富山駅と中心部を周回する市内電車「環状線」
の整備はすでに実現しています。
左の写真は富山ライトレールの岩瀬浜駅で、
バスとの乗り換えが簡単な構造となっています。
右の写真は環状線です。
最近の路面電車は本当にスマートですね
(レトロな電車も走っていました)。
もっとも、北陸新幹線の開業が3月なので、
富山駅周辺はまさに工事ラッシュ。
南北が分断され、駅前も歩きにくい状態でした。
完成すれば南北の通り抜けが簡単になり、
ライトレールと市内電車もつながります
(今は北と南で分かれています)。
実際に乗ってみると、たまたまかもしれませんが、
どちらも利用者が結構多くて驚きました。
地方で車を使わない層というと、高校生以下、
あるいはシニア層というイメージですし、
確かにローカル線の客層はそんな感じです。
でも、そのような乗客の偏りはありませんでした。
環状線は観光客の利用も多かったみたいです
(とりあえず一周乗ってみようという人も)。
富山市のコンパクトなまちづくりについて、
評価するのはまだ早いかもしれません。
本来は財政面も合わせて見るべきでしょう。
参考までに、富山市が2011年に公表した中間報告
によると、
・路面電車の乗車人数は増えた(ただし目標は未達)
・中心商業地区の歩行者通行量は全体では減少
・中心市街地の居住人口は減少
となっています。中心市街地には高齢世帯が多く、
自然減が足を引っ張る結果となっているようです。
駅の整備が進み、公共交通がより使いやすくなると
結果はもう少し違ってくるのかもしれません。
※いつものように個人的なコメントということでお願いします
※いつものように個人的なコメントということでお願いします。
ブログを読んで面白かった方、なるほどと思った方はクリックして下さい。