
新年あけましておめでとうございます。
今年は丙午(ひのえうま)ということで、私の学年はついに還暦イヤーとなってしまいました。もっとも、私自身は2月生まれなので、60歳にはあと1年以上ありますが…
福岡と東京・横浜の2拠点生活はもうすぐ6年になります。移動続きで腰にくるときもありますが、何とか無事に活動できているのは、家族をはじめ私と関わってくださる皆さまのおかげです。
2025年もいろいろなことがありました。
保険アナリストとしては、一昨年に続き書籍を出せたことが大きかったです。今回の『保険ビジネス』は副題に「契約者から専門家まで楽しく読める保険の教養」とあるように、身近な存在にもかかわらず、わかりにくいとされることの多い保険の世界をいろいろな角度からひも解いてみました(詳しくはこちらのブログをご参照)。
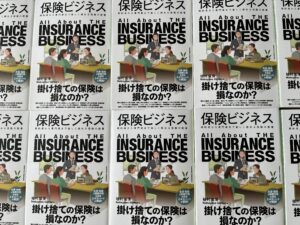
大学教員として最も印象に残っているのは、残念な話ではありますが、単位がそろったので卒論を書かず、ゼミを辞めてしまう学生が続出したことです。こちらのブログ(卒論はコスパが悪い?)でも書いたとおり全国的な現象のようですが、実にもったいない話だと思います。今年はどうなるでしょうか。
プライベートでは、念願のイスタンブール訪問を果たしました。イスタンブールは2つの世界帝国の都として栄えた歴史を持ち、町歩きが非常に楽しいところでした(詳しくはこちらのブログをご参照)。
長崎の軍艦島に上陸できたのも幸運でした。海底炭鉱の島として日本の近代化を支え、その後のエネルギー革命で1974年に閉山・無人島となり、現在はツアーに参加しなければ上陸できません。廃墟となった建物も、かつてそこには人々の営みがあったと思うと胸が熱くなります(詳しくはこちらのブログをご参照)。
それでは本年もよろしくお願いいたします。

※今年の栗きんとんは上手にできました♪
※いつものように個人的なコメントということでお願いします。
ブログを読んで面白かった方、なるほどと思った方はクリックして下さい。




























