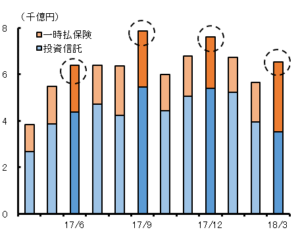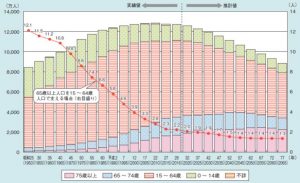アドバイザーとして関わっているRINGの会が今年もオープンセミナーを開きます
(7月6日です)。
昨年は定員の1500人を上回る申し込みがあり、今年もすでに展示ブースはほぼ受付終了とのことですので、ご関心のあるかたはお早めにお申し込みください。
私は今回登壇する予定がなく、当日は久しぶりにセミナーをじっくりと楽しめそうです。
お申し込みはこちら
午前中の第一部「デジタル革命の下で、これからの代理店経営を考える」のプログラム策定に関わったこともありまして、登壇していただく牧野司さんをご紹介します。
牧野さんは昨年まで東京海上グループに所属し、「最先端技術が世界をどう変えていくか」というテーマで調査・研究活動を行ってきたかたです。
2月の損保総研セミナーでの講師紹介には、「東京海上日動に37年間勤務しながらも『自分は今の保険には興味がない』と社内で公言し、独自の視点から最先端技術や新しい働き方について研究しつつ、積極的に社内外で講演活動を行ってこられました」とありました。
東京海上研究所の「研究員ブログ」のなかに、「おとぎ話 in 2045」という、おそらく牧野さんが主席研究員時代に書いたと思われるものを見つけました。
テクノロジーが幾何級数的進化を遂げ、人間の仕事の多くは人工知能とロボットに代替されているかもしれない2045年に、おとぎ話はどう変貌しているかというもので、「アリとキリギリス2045」「ウサギとカメ2045」「花咲か爺さん2045」を読むことができます。
これらを読んで、皆さんはどう感じるでしょうか。
確かに、決められたことをきっちりと勤勉にこなすのは人工知能やロボットが最も得意とする分野でしょうから、これまで人間がやってきた仕事を人工知能とロボットがどんどんやるようになるのでしょう。
そして、そのような世の中では当然ながら人間の働き方も変わっていくのでしょうね。
「デジタル革命」「最先端のテクノロジー」といったテーマで登場するのは、同じくパネリストとして登壇するSEIMEIの津崎桂一さんのように、比較的若いスタートアップのかたというのが王道かもしれません。
でも、それだけではないのがRINGクオリティーです。牧野さん、津崎さん、そしてMATコンサルティングの望月広愛さんの3人がこのテーマで保険業界人に向けて何を語るのか、今から楽しみです。
※全国で活躍する元東急線シリーズ(?)
こちらは秩父鉄道です

※いつものように個人的なコメントということでお願いします。
ブログを読んで面白かった方、なるほどと思った方はクリックして下さい。