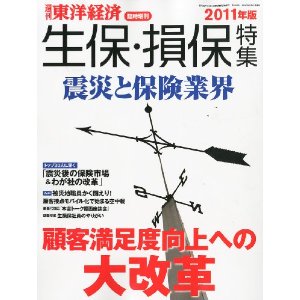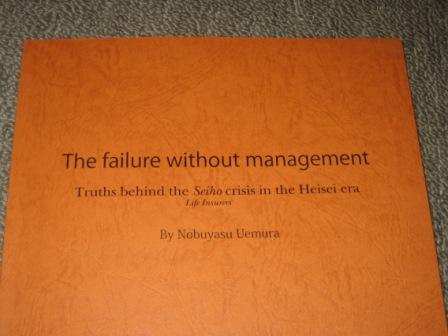先のIAIS(保険監督者国際機構)ソウル年次総会で
日銀総裁が「保険会社と金融システム:中央銀行の視点」
というスピーチをしています
(恥ずかしながら知人に教えてもらいました^^;)
日本銀行のHPへ
講演録(の邦訳)を見ると、いくつか気になるところがありました。
現在のグローバル金融市場の動きを踏まえ、
①現在の低金利をごく例外的な事例と位置づけてよいものか、
保険会社の経営者も規制・監督当局もよく考えなければならない
②ソブリン・リスクの高まりは、保険会社が推進してきたリスク管理の
高度化(=超長期国債の購入によるミスマッチのリスクの削減)の
見直しを迫ることになるかもしれない
③長期的な視点から投資ができる保険会社にとって、
市場のゆがみをとらえて投資に踏み切ることが期待されるが、
仮にそうした行動をとりにくくなっているとしたら、その原因は何なのか、
当局はどのように対応すべきなのか、よく考えなければならない
と話しています。
①はそうだと思いますし、②もわからなくはない(日本のこと?)ですが、
③の「市場のゆがみをとらえて投資に踏み切る」とはどういうことでしょう。
「ファンダメンタルズから乖離していると判断したら投資しろ」
(株式?為替?)ということなのでしょうか。
低金利が続くかもしれないなか、ソブリン・リスクの高まりによって
超長期債購入による金利リスクの削減もままならない、
そんな状況で、保険会社に「市場のゆがみをとらえた投資」
(=リスクをとることですよね)を期待するのが本当にいいのか
「よく考えてみなければなりません」。
もうひとつ、「規制・監督の設計:必要なバランス」のところでは、
「長期調達のウェイトの高い保険会社は、銀行に比べ
金利リスクや流動性リスクにさらされにくい」
という指摘があります。日本では「金利リスク」が顕在化して
「逆鞘問題」が発生しているはずなのですが...
どうも銀行からみた生命保険会社への理解は、
「すぐに返さなくてもいい負債を持つ長期投資家」
「(時価評価しなければ)金利上昇でも大丈夫」
といったもののように感じてしまいます。
※写真は神戸・ポートアイランドです。
日本保険学会の年次大会に参加しています。
※いつものように個人的なコメントということでお願いします。
ブログを読んで面白かった方、なるほどと思った方はクリックして下さい。