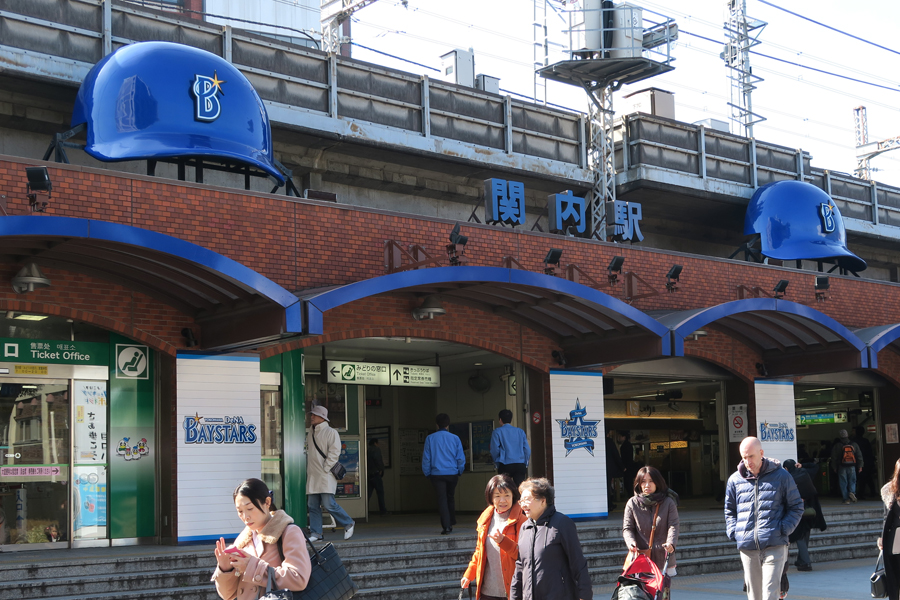先週、3つの生命保険会社が合併し、
「淀川生命」が発足しました...
おわかりですよね。朝ドラの話です。
NHK連続テレビ小説「あさが来た」は、実在した
女性実業家・広岡浅子をモデルにしています。
ドラマではヒロインたちが買収により生命保険業に
進出し、さらに3社合併で規模を拡大しました。
合併で誕生した「淀川生命」のモデルは大同生命で、
実話でも1902年に朝日生命・護国生命・北海生命の
3社が合併し、大同生命が誕生しています。
ドラマでは触れられていないかもしれませんが、
3社合併の背景には1900年の保険業法制定が
ありました。
日清戦争後の好況下に多くの生保会社が乱立。
不健全な会社も目立ったため、保険事業を監督し、
規制するための法律ができたというわけです。
大同生命のサイトによると、監督省庁である
農商務省は、多すぎる生保会社を合併により
整理統合することで、業界全体の財務基盤を
整備する方針を示したとのことです。
ところで、ドラマで「淀川生命」の新聞広告が
大きく映し出されるシーンがあり、そこには
・終身保険
・養老保険
・開運保険
との文字。3つめの「開運保険」に目が留まりました。
私と同じように???と思った視聴者が多かったようで、
大同生命のFacebookチームのかたが開運保険の情報を
アップしています。
<以下、引用です>
—————————-
◎「開運保険」とは?
「開運保険って何?」というお問い合わせがありましたので、
ご紹介します。
当社は1902(明治35)年7月15日に創業しました。当初は
合併した3社の契約を継承しましたが、販売を継続した
商品のうち、死亡保険(注:当時の区分)は終身・養老・
開運の3種類でした。
そのうち「開運保険」は、旧・護国生命から継承した商品で
・満期のときに限り保険金を支払
・満期前に被保険者が亡くなられたときは、以後の
保険料払込を免除
・保険料の払込期間は、全期払込のほか、10年・15年・
20年・25年等の短期払込がある
といったものでした。<「大同生命小史」(昭和42年4月)より>
—————————-
「開運保険」は実際に存在した保険なのですね。
これを見るかぎり、死亡保険という区分ではあるものの、
死亡保険金が出ない、生存保険の一種なのでしょうか。
なかなか興味深いです。
※井の頭公園の桜です。見ごろは今週末でしょうか。
※いつものように個人的なコメントということでお願いします。
ブログを読んで面白かった方、なるほどと思った方はクリックして下さい。