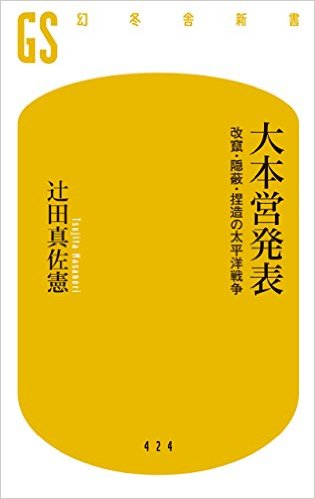写真は東大ですが、早大キャンパスで開かれた、
とある勉強会で、米国には「フラターナル組合」
という組織があると紹介されました。
フラターナル組合は生命保険の提供とともに、
親睦や慈善・福祉などのフラターナル活動を
主な目的とする組織だそうで、日本で言えば、
共済に近い存在です(異論もあります)。
ちなみに慈善的団体ということで、連邦税や
州税などの免税措置がある模様です。
米国の生命保険ファクトブック(2016年)によると、
2015年現在、81のフラターナル組合が存在。
保有契約高は3561億ドル(市場全体の1.7%)、
総資産は1540億ドル(同2.3%)なので、
生保市場における地位は限られています。
ACLIのサイトへ
ただし、最も大きいスライベント・フィナンシャルの
保有契約高は1887億ドル(1ドル115円で約22兆円)、
管理資産は1091億ドル(同12.5兆円)とのことで、
ここはかなりの規模と言えそうです。
同組合はキリスト教徒(元々はルター派)を対象に
保険商品や投資アドバイザリーなどを提供しており、
メンバーは約230万人に達しています。
「賢い経済観念を持ち、寛大な気持ちを持ってもらう」
(wise with money and live generously)がミッションで、
サイトを見ると、教会・地域への支援活動をはじめ、
様々な活動を行っていることがうかがえます。
Thrivent Financialのサイトへ
米国といえば、保険会社との競争条件が平等でない
として、日本の共済制度の改善を求めていますが、
自国内にこのような組合組織が存在するのですね。
※いつものように個人的なコメントということでお願いします。
ブログを読んで面白かった方、なるほどと思った方はクリックして下さい。