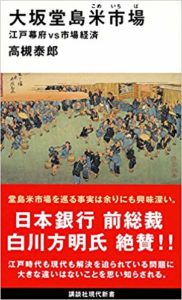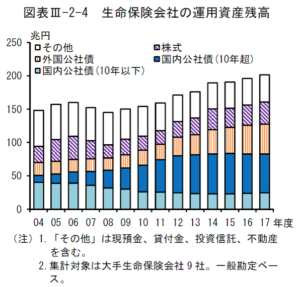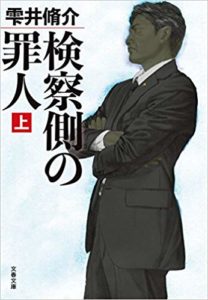保険毎日新聞に九條守氏の「保険業界戦後70年史」の書評を寄稿したところ、あえてご指摘させていただいた部分について、氏を知る匿名のかたから「誤った認識なので謝罪し、訂正したほうがいい」というご連絡をいただき、ちょっとびっくりしました。
私があえてご指摘させていただいた部分とは、第2章第4節「生保破綻のはじまり」にある次のくだりです(本書160ページ)。
「保険料等収支状況(保険料等収入から保険金等支払金を差し引いた金額)を見ると、大半の会社はマイナスであり、『逆ザヤ』状態でした。プラスを維持している生命保険会社は、大手は日本生命保険と安田生命保険の2社、中堅生命保険会社は太陽生命保険、大同生命保険、富国生命保険の3社だけだったのです。この5社は、保険契約者に迷惑をかけず、生き残ったのです」
これに対し、私は書評のなかで、
「保険収支のマイナス、すなわち全体として資金流出が続くのは経営としてあまり望ましい話ではないが、保険会社は保険金等の支払いに備え、責任準備金を確保しているので、保険収支のマイナスは経営の健全性とは関係がなく、まして『逆ザヤ』を示すものでもない」
とコメントしました。書評のなかでこのようなご指摘をすべきかどうか悩ましいところですが、自分の専門分野でもあり、悩んだ末に書かせていただきました。
すると、
「責任準備金を積んだからといって安心な訳ではなく、資産の運用の失敗等で保険金や満期金が支払えない状況や高い予定利率で計算された責任準備金を賄う資産運用ができない状況に陥った場合は、まさしく『逆ザヤ』になってしまいます。特にその『逆ザヤ』が多額になれば、資本の部の資本金、剰余金(利益)から穴埋め補填をすることになるのですが、それもかなわない場合、保険会社は経営危機となり、最悪の場合、倒産するのです。『保険収支のマイナスは経営の健全性とは関係がなく、まして逆ザヤを示すものでもない』と述べておられるのは明らかに誤謬です」
というご指摘をいただきました。
「責任準備金を積んだからといって安心ではなく、責任準備金に対応する資産が十分確保できているかが重要」というのはそのとおりです(加えて、責任準備金そのものの十分性も問われます)。拙著「経営なき破綻 平成生保危機の真実」でも、高予定利率契約への過度な傾斜や資産運用の失敗、ロックイン方式の責任準備金の弱点など、こうした経営危機をもたらした直接的な要因を示したうえで、さらに破綻の根本的な要因を探っています。
ただし、私は書評のなかで「責任準備金を積んでいれば安心」といった話をしたのではなく、「大半の会社は保険収支がマイナスで、逆ザヤ状態だった」「プラスだった5社は生き残った」という記述についてご指摘しています。
生保決算の「保険料等収入⇒責任準備金繰入」「責任準備金戻入⇒保険金等支払金」という流れをご存じであれば、ここであえて保険収支を持ち出すことは考えにくいので、「責任準備金を確保しているので」としました。
保険収支は単にその期に入ってきた保険料収入(月払いも一時払いも含む)から、その期に出ていった保険金や給付金の支払額を差し引いただけなので、責任準備金が十分確保されていれば(もちろん、対応する資産が十分確保されている前提ですが)、マイナスが続いても、保険会社はそう簡単には経営危機に陥ったりしません。
例えば、かんぽ生命の保険収支はマイナスが続いています(2018/3期は保険料等収入が4.2兆円、保険金等支払金が6.9兆円)。大まかにいえば、過去の簡保時代の貯蓄性商品が満期となる一方、いまの低金利時代に魅力的な貯蓄性商品を提供するのは難しく、保障性商品(特約を含む)に力を入れているためです。保険収支としてはマイナスが続いていても、ソルベンシーマージンもEVも堅調であり、高格付けを維持しています。
また、本書では「逆ザヤ」(利差損)とありますが、利差損益、すなわち、運用収益(主にインカムゲイン)と予定利息の差にあたるものが損益計算書のどこに示されるかといえば、運用収益は主に「利息配当金等収入」、予定利息は「責任準備金繰入額(または戻入額)」のなかに含まれていて、少なくとも保険収支とは関係がありません。
ということで、「保険収支のマイナスは経営の健全性とは関係がなく、まして逆ザヤを示すものでもない」ことがご理解いただけるのではないかと思います。
なお、書評の最後に「本書の価値を揺るがすような話ではない」と書いたように、本書はベテラン業界人の目線で戦後70年間の日本の保険業界の歩みをまとめたものであり、とりわけ日々の業務に取り組む今の業界人が読めば、いろいろと気づきを得られるのではないかと考えています。
※写真は京都・島原です。

※いつものように個人的なコメントということでお願いします。
ブログを読んで面白かった方、なるほどと思った方はクリックして下さい。