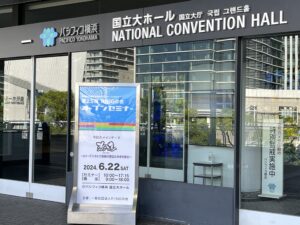前々回のブログでご紹介した8月20日前後のメディア対応に続き、9月1日から4日にかけて、NHK(夜9時のニュースなど)をはじめ、掲題のテーマでいくつかのメディアに登場しました。共同通信の取材にも応じたので、静岡新聞などいくつかの地方紙にコメントが出たそうです(知人に教えてもらいました)。
その共同発のコメントですが、前半部分に訂正があります(申しわけありません)。
「みなし入院給付金の特例は、新型コロナウイルス感染症が未知の病気で社会的に深刻だったタイミングで、医療機関の逼迫(ひっぱく)を回避するために保険業界が社会貢献のような形で導入した」
ではなく、
「みなし入院給付金の特例は、新型コロナウイルス感染症が未知の病気で社会的に深刻だったタイミングで、医療機関が逼迫(ひっぱく)して自宅療養者が出るなかで、保険業界が社会貢献のような形で導入した」
というコメントをしたつもりでした。これは記者さんのせいではなく、私の確認ミスです。
ちなみに後半部分はこうなっています。
「最近は軽症や無症状の感染者も多く、本来は給付金を受け取る対象か疑わしい人も受け取っていることが問題になっている。保険は加入者がお金を出し合って、いざという事態に備える仕組みだ。みなし入院の感染者全てに支払いを続けると、新規で医療保険に加入する人の保険料が値上がりしたり、販売停止につながったりして、加入者が不利益を被る恐れがある」
NHKのコメントは動画のほか、こちらで確認できます。
NEWS WEB「コロナ自宅療養で“入院保険”これからどうなる?」(9月1日更新)
サクサク経済Q&A「【詳しく】新型コロナ 入院給付金見直しって?」(9月1日公表)
コメントの中核部分はこちらになります。
「保険会社が『みなし入院』でも給付金を払うと決めたときはまだ、コロナがどんな病気で、どれくらい深刻なのかが分からなかったため、こうした対応が社会にとって役立つと考えていたのだと思う。しかし、今は症状が重くなくても、陽性と判定されればそれだけで給付金がもらえてしまう状況で、給付金をもらうためにあえて保険に加入する人も出てきている。入院給付金の原資は契約者が払う保険料で、保険料を払っている人と給付金を受け取っている人のバランスが崩れ不公平な状況になっており、正常な状態に戻すという話だと捉えるべきだ」
後段の「保険料を払っている人と給付金を受け取っている人のバランスが崩れ不公平」というのはちょっと変ですが、「保険料と給付金のバランスが崩れているうえ、保険料を負担している人たちのなかで不公平が生じている」と捉えていただければ幸いです。
ちなみに同じNHKでもNEWS WEBとサクサク経済Q&Aは別の取材でして、これは本人でないとわからないかもしれません。

念のため、今回の見直しに関する資料を挙げておきましょう。
1.金融庁「入院給付金の取扱い等に係る要請」(9月2日公表)
生命保険協会、日本損害保険協会、外国損害保険協会、日本少額短期保険協会にあてたもので、「貴協会におかれては、会員各社において、医療機関や保健所の負担軽減に十分配慮しつつ、政府による検討の方向性を踏まえた上で、いわゆる『みなし入院』による入院給付金の取扱い等について、支払対象も含め、可及的速やかに検討が行われるよう周知していただきたい」とあります。
2.生命保険協会「新型コロナウイルス感染症による宿泊施設・自宅等療養者に係る療養証明書の取扱い等について」
上記の金融庁要請を受けて、「生命保険各社においては、医療機関や保健所の負担軽減に十分配慮しつつ、いわゆる『みなし入院』による入院給付金の支払対象も含めた取扱い等について、 検討が行われるよう周知しています」とあります。日本損害保険協会のリリース文も、この部分に関してはほぼ同じです(「周知」ではなく「依頼」となっていますが)。
各社の対応はおそらく検討中で、まだサイトでは確認できませんでした(5日現在)。
※熊本城の修復もだいぶ進みましたね。

※いつものように個人的なコメントということでお願いします。
ブログを読んで面白かった方、なるほどと思った方はクリックして下さい。