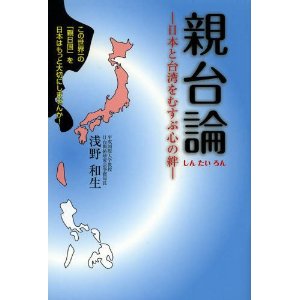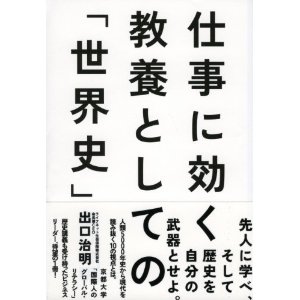GW直後ということで、最近読んだ本のご紹介です。
1.「世界の経営学者はいま何を考えているのか」
世界のビジネススクールの最前線にいる「経営学者」たちが
どんな研究に取り組んでいるのか、わかりやすく紹介した本です。
・アメリカの経営学者はドラッカーを読まない
・ハーバード・ビジネス・レビューは学術誌ではない
・経営学には教科書がない
これだけでも「目からうろこ」ですが、私がなるほどと思ったのは
「日本の経営学と海外の経営学」のところです。
日本の経営学がケース・スタディーを重視する風潮が強いのに対し、
米国を中心とした世界の経営学の主流は、理論仮説を立て、
それを統計的な手法で検証するアプローチなのだそうです。
著者の入山さんは、両者が互いの長所短所を補い合うことが重要
と述べているものの、
「現在欧米を中心としたトップスクールにいる経営学者の多くは
(彼らが考える意味での)科学性を重視しており、そのために
『理論→統計分析』の演繹的アプローチが支配的である」
と説明しており、どこかで聞いた話だなあと。
ただ、入山さんもどこかで書いていましたが、企業の経営は
自然現象ではなく、人間や人間の集団が行うものですよね。
仮定に基づいた統計分析でどこまで本質に迫れるのか、
各章で紹介された世界の経営学のフロンティアをみると、
まだまだ発展途上の分野であることもわかりました。
2.「申し訳ない、御社をつぶしたのは私です」
副題は「コンサルタントはこうして組織をぐちゃぐちゃにする」。
職業柄ドキドキするタイトルですが、単なるコンサル批判ではなく、
従来の経営コンサルティングの問題点を指摘したうえで、
コンサルティング業務の望ましいあり方や、クライアントと
コンサルタントの正しい付き合い方を提唱したものです。
本書にも様々な経営理論が出てくるのですが、
著者のカレン・フェラン氏は自身の長年の経験等から、
過去を懺悔しつつ、これらを一刀両断しています。
本書には、
「コンサルティングが役に立つとき、役に立たないとき」
「危険なコンサルタントの見抜き方」
なんて表も付いていて、これだけでも参考になりそうです。
3.「アクチュアリー・桑山啓介の転職」
このところ専門職として人気が高まりつつあるアクチュアリー。
本書は「損害保険アクチュアリー」の世界を描いた珍しい本です
(初版は2008年)。
「筆者のこれまでの経験や見聞を踏まえたフィクション」とはいえ、
私も20年以上、保険業界とお付き合いしていますので、
本書で描かれた中堅損保や外資系損保の社内の状況は
ものすごくリアルに感じました。
中堅損保から外資に移った本書の主人公は、
再び日本社に転職するところで終わっています。
その後どうなったのか、続編が気になるところですね。
なお、筆者のHPがあり、そこで補足情報が得られます。
鷹巣怜のホームページ
<番外編> 「親台論-日本と台湾の心の絆」
台湾に行く前に勉強しようと思い、関連書籍を探してみると、
圧倒的に多いのは「グルメ関連」でした^^
次に目立つのは、台湾を題材にしつつ、日本のありかた
(特に対中、対韓関係)を論じているものでしょうか。
本書もタイトルからして後者のジャンルに入るとはいえ、
イデオロギー色が薄く、日台関係について勉強するには
いい本だと思います。
確かに私の経験からしても、台湾の皆さんは日本や日本人に
好意的だという印象がありますし、台湾の町を歩いていると
あちこちに「日本」が見つかります。大事にしたいお隣さんですね。
※台湾といえばマンゴー氷です♪
※いつものように個人的なコメントということでお願いします。
ブログを読んで面白かった方、なるほどと思った方はクリックして下さい。