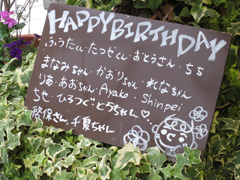前々回に続き、生保の四半期開示から。
大手生保の新契約業績の推移を見ると、
第一生命の新契約高(保険金額ベース)が
2014年1-3月期から急減していることがわかります。
調べてみると、昨年12月から主力商品が変わり、
特約から定期保険(=死亡保障)がなくなる一方、
7大リスク(がん、脳卒中、死亡など)をカバーする
「アシストセブン」を付加する形になっていました。
新契約高は基本的に死亡保険金額なので、
おそらく新商品は新契約高に反映されにくいのでしょう。
他方で第三分野の年換算保険料が前年同期よりも
伸びているので、第三分野・生前給付シフトが
強まったと言えそうです。
新商品といえば、明治安田生命もこの5月から
主力商品を切り替えています。
主契約のアカウント部分をなくし、更新型の各種特約を
組み合わせるタイプにしました。
同社は2000年にアカウント型保険を発売しました。
自在性が売りだったのですが、結果的に保険契約が
小粒となり、平均保険料の水準が下がったようです
(商品特性によるのか、販売戦略なのかは不明です)。
新商品も自在性を訴求しているようですが、
特約の組み合わせだけで構成されています。
第一生命とは違い、こちらは定期保険特約がありますが、
特約の一つに死亡保障があるという感じなので、
やはり第三分野・生前給付シフトが進むのかもしれません。
他の大手2社の四半期開示も主力商品と合わせて見ると
なかなか味わい深いので、機会がありましたらぜひご覧下さい。
累積ベースから四半期ベースにするのが面倒ですけど、
せっかくの開示ですので、大いに活用しましょう。
※写真は台北MRTの温泉仕様と、台鉄の貨物列車です。
※いつものように個人的なコメントということでお願いします。
ブログを読んで面白かった方、なるほどと思った方はクリックして下さい。