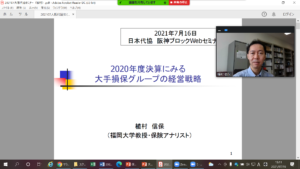7日の日経新聞に「損保大手、災害多発に備え」「危険準備金8%増」とあったので、決算データを確認してみました
(ちなみに危険準備金と異常危険準備金は別物なので、「異常」を省略したらダメですね)。
異常気象への備えということなので火災保険の異常危険準備金を確認したところ、繰入・取崩をネットした積増額は以下のとおりでした。
東京海上日動 35億円( 75億円)
三井住友海上 44億円(▲81億円)
あいおいND ▲1億円(▲48億円)
損保ジャパン 36億円( 88億円)
*( )は前年同期の積増額
各社が総じて異常危険準備金を繰り入れたのは確かです。ただ、数字の大きさからみて、異常気象への備えを急いでいるという感じではなさそうですね。記者さんがどうしてここに注目したのか、ちょっとよくわかりませんでした。
そもそもリスクに備えた支払余力という観点からすると、何も異常危険準備金ではなくてもかまいません。各社が公表するESR(経済価値ベースのソルベンシー比率)には多少の余裕がありそうなので(推測を含む)、積み増しを急ぐ理由はないのかもしれません。
国内損保事業で言えば、注目は火災保険の収入保険料が伸びていることでしょうか。
元受正味保険料の前年同期比はご覧のとおりです。
東京海上日動 +10.0%(+5.4%)
三井住友海上 +5.6%(+4.6%)
あいおいND +6.7%(+5.9%)
損保ジャパン +8.8%(+3.1%)
*( )は2020年4-6月期の伸び率
料率引き上げ効果が大きいのか、あるいは、コロナ禍でも契約を伸ばしているのか、今ある情報だけでは何とも言えないので、引き続きよく観察したいと思います。特にコマーシャル分野がどうなっているのか知りたいところです。
注目の(?)自動車保険の損害率は以下のとおりでした。昨年度の異常値から戻るのは予想どおりとはいえ、一昨年度に比べるとかなりの低水準です。料率引き上げ効果のほか、コロナの影響が続いているのかもしれません。
東京海上日動 56.5% ⇒ 46.2% ⇒ 52.3%
MSAD合算 54.8% ⇒ 47.1% ⇒ 50.7%
損保ジャパン 63.1% ⇒ 48.1% ⇒ 53.9%
*2019年度⇒2020年度⇒2021年度
*E/Iベース
※長崎はトラムが走る町です。もうすぐ新幹線も走ります。

※いつものように個人的なコメントということでお願いします。
ブログを読んで面白かった方、なるほどと思った方はクリックして下さい。