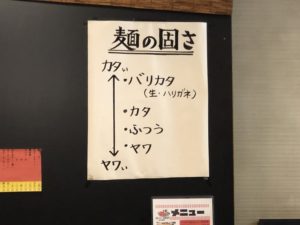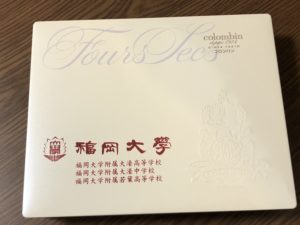経済価値ベースのソルベンシー規制の導入などについて検討を行ってきた有識者会議の報告書が公表されました。
「ソルベンシー規制の今後あるべき姿として、経済価値ベースで保険会社のソルベンシーを評価する方法を目指すべきである(5ページ)」と提言した2007年4月の報告書(PDF)の公表から10年以上がたち、「保険会社の内部管理において経済価値ベースの考え方を取り入れる動きが進む一方、保険監督者国際機構(IAIS)における国際資本基準(ICS)をはじめとする国際的な動向の進展もみられた」(報告書1ページより)なかで出されたものです。
個人的な注目点をいくつか取り上げてみましょう。
検討タイムラインの設定
2007年の報告書にも「平成22年(2010年)を見据えて不断の作業を進める」とありましたが、今回の報告書では2025年の導入を前提に、より具体的なタイムラインが示されました。
・2022年頃 制度の基本的な内容を暫定的に決定
・2024年春頃 基準の最終化
・2025年4月より施行
まずは2022年をターゲットに、金融庁が来月からの2事業年度で制度の基本的な内容を詰めていくことになります。
第1の柱と第2の柱の関係
報告書では「保険会社の内部管理のあり方も踏まえた多面的な健全性政策」を念頭に、新たな健全性政策の内容を「3つの柱」の考え方に即して整理しています。
・第1の柱(ソルベンシー規制)
・第2の柱(内部管理と監督上の検証)
・第3の柱(情報開示)
第1の柱と第2の柱のバランスは結構難しくて、第1の柱のあり方によって、報告書でも懸念する意見があるように、保険会社のリスク管理の高度化が停滞する可能性があります。さりとて「第2の柱で見ればいい」となってしまうと、監督介入が遅れたり、恣意的なものとなったりしてしまいます。
「経済価値ベースの第1の柱は2025 年に導入することを前提として検討を進めていくべきである。一方、それまでに保険会社の内部管理態勢及び金融庁の監督態勢の双方を高度化し、経済価値ベースの制度への円滑な移行を促す観点からは、第2の柱に関する取組みは、第1の柱の導入を待たずに早期に開始することが適当である」(33ページ)
「リスクとソルベンシーの自己評価(ORSA)上では、割引率につき標準モデル上の手法(終局金利(UFR)に基づく補外等)以外の手法も用いて評価を行うことや、自社の保険契約・運用資産のポートフォリオの特性を反映した粒度の高いデータに基づく、より精緻なリスク計測手法を用いること等も視野に入りうる」(35ページ)
報告書のこうした記述を見るかぎりでは、第1の柱はあくまで「最大公約数」であり、リスク管理の高度化を促すフェーズでは、第2の柱が重要という整理のようです。
「厳格化」には触れず
2007年4月の報告書(PDF)では、ソルベンシー・マージン比率の信頼性を向上させて行く努力が必要として、次の記載がありました。
「段階的な取組みの一歩として、例えば95%程度を信頼水準引上げの目標とするのであれば、保険会社に対する財務上の影響や、健全性評価に対する信頼性の向上の両面からみて適当ではないかと考えられる。(中略)そして、経済価値ベースのリスク評価への移行を前提とした上で、国際的な動向も見据え、更に信頼水準を引き上げていくことが適切である」
所要資本(リスク量)の計算を90%から95%へ引き上げるのはあくまで段階的な取り組みの一歩であり、経済価値ベースの規制に移るとともに、さらにハードルを上げることが提案されていました。
今回の報告書には、第1の柱における信頼水準について記載がありません。
ただ、「国内規制における標準モデルについては、ICSと基本的な構造は共通にしつつ検討を進めていくことが適当である」(14ページ)とあり、これまでの国内フィールドテストでもICSを参照してきたことから、普通に考えればICSの「99.5%」がそのまま採用されるのでしょう。
20年に1回から200年に1回の水準に上がるので、前回の変化よりも大きそうですね。
※宮崎県産の完熟マンゴーと福岡県産のブルーベリーです♪

※いつものように個人的なコメントということでお願いします。
ブログを読んで面白かった方、なるほどと思った方はクリックして下さい。