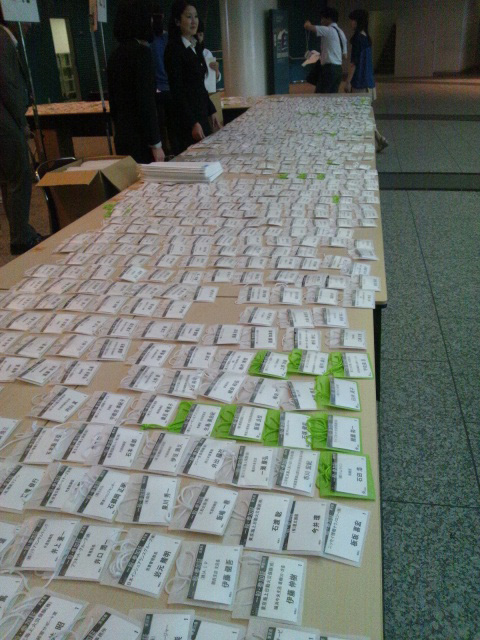今回も金融庁関連で恐縮です。
年度替わりでいろいろと公表されるものですから…
昨年9月に公表された金融モニタリング基本方針の成果をまとめた、
「金融モニタリングレポート」が公表されました。
金融庁HPへ
本レポートは、
・金融システムの現状
・業態別の金融モニタリングの概要
・テーマ別の水平的レビューの概要
・当局としての取組み
という構成で、全部で111ページあります。
業態別のところでは、「3メガバンク」では海外G-SIFIsとの対比
(海外G-SIFIsについてかなり調べたようですね)が目立ち、
「グローバルな金融システムのなかでのメガバンク」という
金融庁の意識が強く伝わってきます。
また、「地域銀行」では、モニタリングの一環として
大口融資先へのヒアリングなども行っており、
ビジネスモデルの中長期的な持続性を探っています。
これらに比べると、保険会社(特に生保)のモニタリングは
あまり踏み込んだ話がなく、ちょっと拍子抜けしました。
問題がなかったということでしょうか?
あえて言えば、損保の統合的リスク管理(ERM)の記述が、
「経営戦略と一体となったリスク管理態勢については、
総じて整備途上」
「エマージングリスクについては、リスクの洗出しなどの
取組みを開始した段階」
など、前回のブログで取り上げた「ORSAヒアリング」と違い
「損保は進んでいる」というトーンではなかったこと。
生保に比べれば進んでいるとしても、絶対評価としては
まだまだということなのでしょうか。
もう少し記述があるといいのですが、10行ちょっとでは…
テーマ別の水平的レビューで私の目を引いたのは、
「内部監査」「ITガバナンス」のところです。
メガバンクの項目と同様に、海外G-SIFIsとの対比を通じ、
不十分なところを浮き彫りにしようという手法が見られます
(ITガバナンスの「連邦型」「中央集権型」など)。
全般的に、今回は海外大手金融機関の経営管理の把握に
力を入れたことがうかがえますね。
ちなみに今後についてですが、3メガバンクは
「来事務年度においても、引き続き・・・」
とある一方、保険会社では、
「引き続き、契約者や経営に影響を与える顧客保護等管理態勢
や経営管理態勢を中心にモニタリングを強化する必要がある」
「保険会社は規模やビジネスモデルが多様であることから、
業務特性やリスクプロファイル等を踏まえ、リスクの高い分野に
重点を置いたモニタリングを徹底する必要がある」
これだけを見ると、大手以外の会社に対するモニタリングを
強めていくのではないかと思えます(あくまで私の想像です)。
※松坂屋の姿がなく、免税店(ラオックス)が賑わっており、
銀座の中央通りはだいぶ様子が変わりましたね。
※いつものように個人的なコメントということでお願いします。
ブログを読んで面白かった方、なるほどと思った方はクリックして下さい。