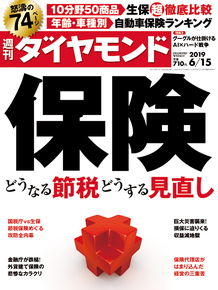右足を痛め、歩くのが不自由になって10日ほどたちました。
せっかくなので、東京近郊に住む私が、通勤・外出時に感じたこと、気が付いたことを残しておこうと思います。
優先席の世界
優先席に限らず、大変そうな人には席を譲るのが当然なのかもしれません。そうは言っても一般席はこわいので、努めて優先席に向かっています。
ただ、朝の電車はピークをずらしても混んでいるので、電車を選ばないとそもそも優先席に近づけないのですね(東急東横線の場合)。
それでは優先席にたどりつけば座れるかといえば、「座れることのほうが多い」といったところでしょうか。途中駅なので空席はなく、杖を持って乗ってきた私に気が付いてくれたかたは、ほぼ席を譲ってくれますが、全く気が付かない(少なくともそう見える)かたもいます。
なかには後ろからトントンとタッチして、「こちらへどうぞ」なんて言ってくれるかたもいて、先週はかなり辛かったので、これは涙が出るくらいうれしかったですね。
この気持ちを忘れないようにしたいです。
もっとも、一見すると大変そうに見えなくても、実は大変なかたもいるのでしょう。私だって、もし杖を持っていなければ、「なんでコイツは優先席に座っているんだ」と思われるだろうなあと、ついつい考えてしまうので、見るからに大変そうではない人があの席に座るのは相当なプレッシャーかもしれません。
優先席から見た朝の東横線は、高齢者が意外に少ない一方で、妊婦さんが目立ちます。
ところが新橋駅からの都営バスはシニアが多くて、むしろ席を譲ったりすることもありました(1回だけですが)。
地下鉄のバリアフリー状況
行動範囲が限られているので、あくまで私が体験した事例としてお読みください。
先週は100メートル進むのにものすごく時間がかかったうえ、階段なんかとんでもない(特に下り)という状態だったのですが、地下鉄やJRには苦しめられました。
まず、会社の最寄り駅(築地市場駅)に泣かされました。地上からの出入口が3か所あって、そのうち1か所にエレベーターがあります。たまたま会社から最も遠い出入口で、何とかたどり着いてエレベーターに乗ると、そこから改札口まで100メートル歩かなければなりません。古い駅ではないのに、なぜこんな構造なのでしょうか。

それから同じく都営の大門・浜松町駅では、JRに乗り換えようと地上に向かうエレベーターに乗ったら、途中から階段になっていて、あとは上がるのも下がるのも階段を使うしかありません。
こうした出入口は他にもいくつもあるようで、おそらくどこかにバリアフリールートがあるのだと思いますが、事前に調べておかないと大変なことになります。
都営ばかりで恐縮ですが、神保町駅では改札を入ろうとしたら、親切な駅員さんに、「ここは階段だけですが、もう一つの改札ならエレベーターがありますよ」と教えてもらったのはよかったのですが、その「もう一つの改札」が遠くて涙が出ました。
まあ、これは仕方がないのかもしれませんが、そもそも駅には下りのエスカレーターがあまりに少ないですね。東京メトロの大手町駅でしたか、せっかくエスカレーターが2つあるのに、どちらも上りでガッカリしたこともありました。
横断歩道を渡り切れるか
地上にも難所がいくつもありました。都心部の歩道は広いので、あまり困るようなことはなかったのですが、地元では歩道が狭いうえに起伏が激しく、段差も多いので、体力を消耗してしまいます。歩道って、どうして車道よりも高くなっているのでしょうか。
都心部は歩道が広いだけでなく、車道も広いので、信号が青のうちに横断歩道を渡り切れるかというプレッシャーを何度も感じました。
バリアフリー状況もそうですが、恒常的に歩くのが不自由なかたは、いつもこのような思いをしているのでしょう。横断歩道を渡り切れないなんて、考えたこともありませんでした。

そうそう、何をするにも時間がかかってしまうのには閉口しました。
特に雨の日は、杖と傘で両手がふさがってしまい、ただでさえ動作が遅いのに、電車やバスに乗るにしても、コンビニで買い物をするにしても、やたらと時間がかかってしまいます。当初はどうしても自分にイライラしてしまいましたが、これにはすぐに慣れました(周りには迷惑をかけているのでしょうけどね)。
※いつものように個人的なコメントということでお願いします。
ブログを読んで面白かった方、なるほどと思った方はクリックして下さい。