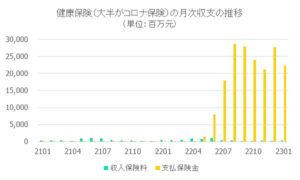私のゼミでは年に数回、金融・保険分野の実務家をゲストとしてお招きしています。
先週(22日)は福岡財務支局の永松さんに金融リテラシー向上をテーマにした授業をお願いしました。その様子がニッキンオンラインで紹介されています(こちら)。
グループワークには福岡信用金庫の若手職員にも加わっていただき、中身の濃い授業になりました。関係者の皆さま、ありがとうございました。
さて、東急向けの保険契約で保険料の調整行為が行われていたというカルテル事件が発覚しました。
幹事会社である東京海上日動をはじめ、共同保険に関わっていた保険会社が関与を認め、リリースを公表しました
(三井住友海上、あいおいニッセイ同和、損保ジャパン)。
共同保険とは、複数の保険会社が分担してリスクを引き受けるもので、保険会社は引受割合に応じて責任を負います(連帯責任ではありません)。顧客の意向で入札が行われるのが一般的で、本件では顧客が入札時の保険料水準に疑念を持った(4社の保険料が同水準だった)ことを契機にカルテルが発覚したそうです。
東京海上日動によると、複数の社外弁護士を起用した特別調査委員会を設置し、事実関係の確認に努めているとのことです。
現時点でわかっていることとして、4社とも東急の株式を政策目的で保有し、最も保有数が多い東京海上日動が主幹事を務めているという話があります。ただし、上位10社を占めるほどの大株主ではありません。
東京海上日動 4,388,338株(2023/3末)
三井住友海上 1,467,105株(2022/3末)
あいおいND 913,814株(2022/3末)
損保ジャパン 3,235,785株(2023/3末)
ところで、各社のリリースにも報道にも「代理店」が出てこないのはどうしてなのでしょうか。
一般的には大企業向け保険の多くが直扱い、すなわち、保険会社が企業に直接販売する、というのではなく、企業がグループ内に設立した企業代理店(機関代理店)を通した契約となっています。東急グループにも東急保険コンサルティングという専業保険代理店があり、2022年3月期の売上高は17.4億円に上ります。
保険料率が自由化される以前であれば、大企業といえども保険会社と価格交渉する余地がなかったので、企業は代理店を作り、保険会社から代理店手数料を受け取るのが合理的だったのかもしれません。しかし、料率が自由化された今では、価格交渉によって保険料が減ると、企業代理店の収入も減ってしまいます。もちろん企業からすれば、優先すべきは自らのリスクマネジメントを効率的に行うことであり、そのための専門人材(リスクマネジャー)も必要なのですが、他方で企業代理店は総じて企業OBの受け皿となっていて、専門的な仕事は保険会社の営業担当社員や保険会社からの出向者が行っていたりします(東急グループの話ではなく、あくまで一般論です)。
このような市場慣行があるなかで今回の件が生じたのかどうかはわかりません。ただ、大企業向け損害保険の世界は外部から見て謎が多いのは確かです。
※写真は東京・新橋駅です。

※いつものように個人的なコメントということでお願いします。
ブログを読んで面白かった方、なるほどと思った方はクリックして下さい。