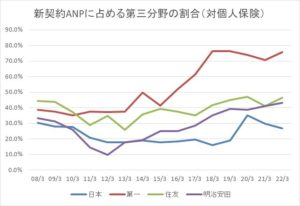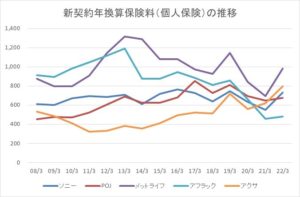この週末(25日)は日本保険学会九州部会の例会があり、福岡大学での対面&オンライン(zoom)開催でした。こちらから当日のプログラムやレジュメをご覧いただくことができます(確か期間限定だったと思います)。
2人の報告者のうち、最初に登壇した神戸大学の若土先生の報告「活版印刷技術が及ぼした中世海上保険証券への影響」は、『海事交通研究』第70集に掲載されたこちらの論文(PDF)のアップデートだったようです。中世イタリアをはじめ、スペイン、ポルトガル、オランダ、ドイツなど、これだけの古文書(主に保険証券)を発掘するにはかなりの労力がかかったのではないでしょうか。
『海事交通研究』の論文を拝見したところ、15世紀にグーテンベルクが発明した活版印刷技術が、それまで全て手書きだった海上保険証券の定型部分に導入されていったことを、文献だけではなく、若土先生自らが収集した史料をもとに検証したものでした。
グーテンベルクの活版印刷技術は火薬、羅針盤とともに「中世の3大発明」の1つと言われ、その後のヨーロッパ社会に大きな影響を与えました。この技術を使えば写本よりも早く、安く、大量に読み物を作ることができるので、情報が広く一般に普及するようになります。確かにこれは革命的です。
ただ、海上保険の保険証券を早く、安く、大量に印刷する必要はなさそうなので、両者がどう結びつくのかが疑問でした。これに対し、本論文では16世紀末のアムステルダムで保険証券の定型部分に活版印刷が利用されたことについて、2つの理由を挙げています。
「登記の手間の削減や保険手続きの簡素化や迅速化といった時代のニーズに対応できるよう、恐らく証券書面の統一化を図るため証券上の定型的な部分に活版印刷技術を導入していったのではないかと筆者は考えている」
「取引市場のエリアが拡大し(中略)有力商人たちは企業化しネットワーク網が広がり、契約した重要な補償内容を現地・本部のいずれでも確認できる需要が強まり、証券の定型部分を活版印刷によって記載する動きに繋がったのではないかとみている」
いずれもまだ仮説のようですが、興味深いですね。僭越ながら研究が進み、活版印刷技術と保険の関係がより明らかになることを期待しています。
※アジサイにもいろいろな種類があるのですね。

※いつものように個人的なコメントということでお願いします。
ブログを読んで面白かった方、なるほどと思った方はクリックして下さい。